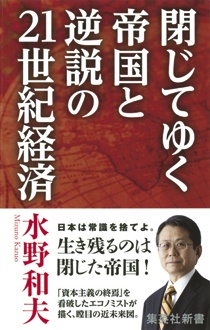2017年7月号掲載
閉じてゆく帝国と逆説の21世紀経済
- 著者
- 出版社
- 発行日2017年5月22日
- 定価858円
- ページ数270ページ
※『TOPPOINT』にお申し込みいただき「月刊誌会員」にご登録いただくと、ご利用いただけます。
※最新号以前に掲載の要約をご覧いただくには、別途「月刊誌プラス会員」のお申し込みが必要です。
著者紹介
概要
「世界全体を豊かにする方法は、グローバリゼーションしかない」。これまで、こうした言説は世界の常識として肯定的に語られてきた。だが近年、米国や英国など先進各国で内向きの動きが目立つ。その背景にあるものとは? 従来の資本主義が限界を迎える中、世界経済が向かう先とは? エコノミストの水野和夫氏が考察する。
要約
「閉じてゆく」時代
グローバリゼーションを否定するかのような動きが、先進国の国民の中で急速に広がっている。
イギリスの国民がEU離脱を選択し、アメリカでは不法移民の国外追放や、外国製品に対する関税引き上げを唱えたトランプを大統領に押し上げたことで、その潮流は誰の目にも明らかになった。
これまでグローバリズムの旗振り役だった英米両国の国民がともに、グローバリゼーションに疑問符を突きつけたのだ。つまり、これは世界に対して「閉じる」という選択である。
1970年代から約40年にわたって世界に影響を与えてきた新自由主義的な考え方は、1991年にソビエト連邦が崩壊すると、世界の「常識」として、あらゆる経済活動の前提条件のように考えられてきた。
その新自由主義的なイデオロギーをうまく包み込んだのがグローバリゼーションである。「これからの企業はグローバルに活動しなければ、競争に負ける」「世界全体を豊かにするにはグローバリゼーションしか方法はない」といった具合だ。
それがここにきてグローバリズムに背を向けようという意識が先進各国で広まったのは、なぜか。
大きな歴史の見取り図をもとにいえば、資本主義が最終局面を迎えていることと無縁ではない。
投資をしても利潤を得ることが極めて困難になり、資本の側がわずかでも利潤を得ようと国境の壁を越え、なりふりかまわぬ行動を取るようになった。これこそがグローバリゼーションの正体で、元来、国家が市場を適度に規制することで保護されてきた社会の安定が脅かされている。
そうなると、国内の格差や貧困という形でしわ寄せを食うのは一般の国民である。そうした現実が先進国の中で明らかになってきたために、政治の上でも「反グローバリズム」を標榜する党派が集票できるようになった。
つまり、各国の国民はグローバルな資本がもたらす不安定性から自分たちを守ってくれる「国民国家」の強化を求めているのである ―― 。