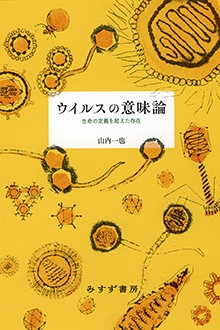2020年5月号掲載
ウイルスの意味論 生命の定義を超えた存在
著者紹介
概要
ウイルスの生と死は、独特だ。天然痘やインフルエンザなど、たびたび世界的流行を引き起こしたが、細胞外では活動せず、感染力を失ってすぐ死ぬ。また近年、3万年以上も冬眠していたウイルスが、再び増殖し始めたという。本書は、単なる病原体ではなく、生命体としての視点から、ウイルスの驚くほど多様な生態を紹介する。
要約
ウイルスの奇妙な“生”と“死”
ウイルスには、「正体不明の不気味な病原体」というイメージがつきまとう。エボラ出血熱の発生や新型インフルエンザの出現といったショッキングなニュースばかり注目され、ウイルスの多様な生態が正しく伝えられていないためである。
そこで、ウイルスの真の姿を紹介しよう。
借り物の生命
ウイルスは、ウシの急性伝染病である口蹄疫とタバコの葉に斑点ができるタバコモザイク病の原因として、19世紀末に初めて発見された。そして、ラテン語で「毒」を意味する「ウイルス」と名付けられた。
それから半世紀余りの間、ウイルスは微小な細菌と考えられていた。しかし、実際にはウイルスと細菌はまったく別の存在である。
細菌をはじめ、生物の基本構造は「細胞」だ。細胞は、栄養さえあれば独力で2つに分裂し、増殖する。増殖できるのは、細胞膜の中に細胞の設計図(遺伝情報)である核酸(DNA)やタンパク質合成装置(酵素)などを備えているからだ。
一方、ウイルスは独力では増殖できない。タンパク質を合成する装置を備えていないからだ。
しかし、ウイルスは、ひとたび生物の細胞に侵入すると、細胞のタンパク質合成装置をハイジャックして大量に増殖する。そのため、ウイルスは「借り物の生命」と呼ばれることもある。
ウイルス粒子が細胞外にある時、それは単なる“物質の塊”だ。生命らしい活動を行うことはない。しかし一旦、細胞に入ると生き生きと活動し始め、膨大な数の「子ウイルス」を産みだす。
3万年も眠っていたウイルス
2014年、フランスのエクス・マルセイユ大学のジャン=ミシェル・クラブリーは、3万年以上前の凍土層の土壌サンプルをアメーバに加えて培養を行った。すると、3万年以上も冬眠していたウイルスが、アメーバの内部で再び増殖を始めた。
2015年には、同じ凍土層から別のウイルスをアメーバ培養で分離した。
相次いで2種類の太古のウイルスが見つかり、しかも生きていた。これは、温暖化で溶けた凍土層から、太古のウイルスが他にも出てくる可能性があることを示す。古代のウイルスがよみがえり、ヒトに病気を起こすことも、ないとは言えない。