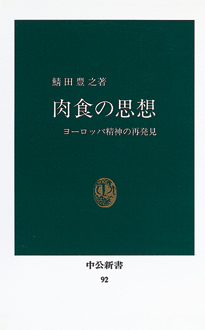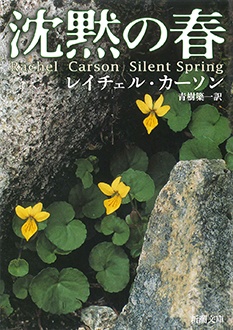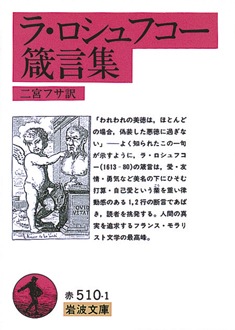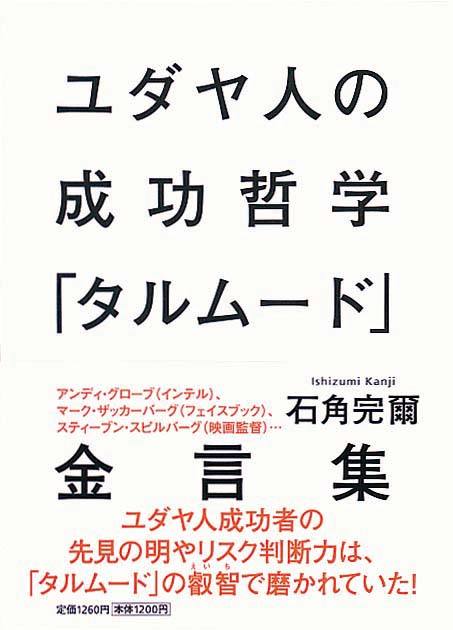2014年11月号掲載
肉食の思想 ヨーロッパ精神の再発見
- 著者
- 出版社
- 発行日1966年1月25日
- 定価770円
- ページ数176ページ
※『TOPPOINT』にお申し込みいただき「月刊誌会員」にご登録いただくと、ご利用いただけます。
※最新号以前に掲載の要約をご覧いただくには、別途「月刊誌プラス会員」のお申し込みが必要です。
著者紹介
概要
豚の頭を平気で口にする一方、動物愛護運動にも熱心 ―― 。こうしたヨーロッパ人の思想の原型を、「肉食」という彼らの食生活から探った。動物を殺すことではなく、不必要な苦痛を与えることこそが残酷。動物屠畜への抵抗感をなくすため、人間と動物の間に一線を画し、人を全ての上位に置く人間中心主義が生まれた等々、“食”の視点から欧州の思想を見直す。
要約
ヨーロッパ人の肉食
日本人の食生活は著しく洋風化したといわれる。しかし、洋風化はあくまで洋風化であり、日本人の食事がヨーロッパ人と全く同じになったのではない。日本人の肉食は、ままごとのようなものだ。
日欧の肉食率の違いの源を探るには、極限状況を見るのが一番よい。
例えば、第1次世界大戦中のパリ。開戦初頭、いきなりドイツ軍をわずか22kmしか離れていない地点に迎えたパリは、大騒動だった。その時、パリの孤立に備えてどんな準備がなされたのか。
この点について、当時フランスに滞在した島崎藤村はこう書いている。「ブウロオニュの森には牛、豚、羊の群が籠城の用意に集められた」。
日本で籠城といえば、昔から、まず用意されるのは米・塩・水である。いくら肉食好きにしても、パリではなぜ、危急存亡の時まで、小麦や小麦粉を貯えるだけですませないのだろうか。
考えられるのは、ヨーロッパと日本との食生活の違いだ。日本では、米飯は主食である。米飯を食べながら、魚・肉・野菜などの副食をとる。副食が足りなければ、塩をかけてでも、米飯を腹いっぱい詰め込めばよい。だから、籠城の場合は米飯さえ確保すれば、後はなんとかなる。
ところが、肉食率の高いヨーロッパでは主食的なものがはっきりしない。パンの役割は日本の米飯とまるで違う。西洋料理のコースを見ればわかるが、パンを食べるのはスープが終わってから、肉・魚料理が出ている間だけだ。サラダを食べ始めたら、残っているパンは持っていかれてしまう。
日欧の肉食率を大きく隔てるのは、主食と副食を区別するか、しないかの一点に尽きる。日本人は主食だけである程度満腹するから、ままごと肉食でやっていけるのである。
一方、穀物生産力が低かったヨーロッパでは日本のような主食観念は生まれようがなかった。
ヨーロッパ人の肉食率が高いのは、決して彼らが恵まれていたためではない。風土的条件が、彼らに穀物で満腹することを許さなかったのである。