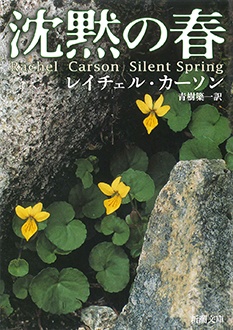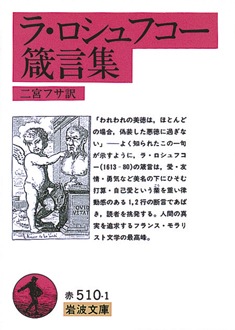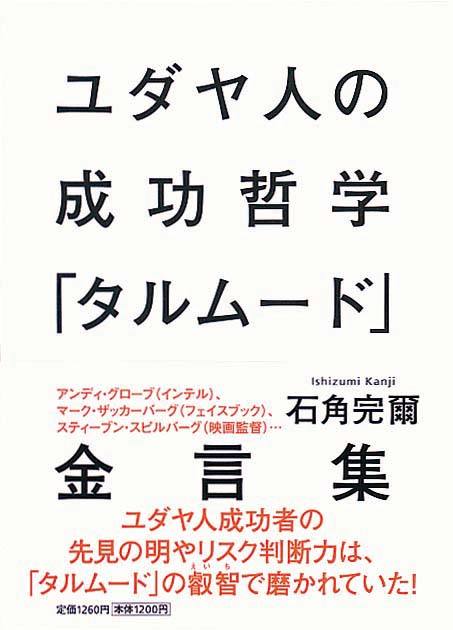2015年2月号掲載
教養としての宗教入門 基礎から学べる信仰と文化
- 著者
- 出版社
- 発行日2014年11月25日
- 定価924円
- ページ数252ページ
※『TOPPOINT』にお申し込みいただき「月刊誌会員」にご登録いただくと、ご利用いただけます。
※最新号以前に掲載の要約をご覧いただくには、別途「月刊誌プラス会員」のお申し込みが必要です。
著者紹介
概要
書名通り、「教養としての宗教」ガイドだ。「物事の理解には、深さもさることながら、広さも大切である」。こう語る宗教研究者が、外国人と接する際、知っておきたい世界の主な宗教を、マクロな視点から“浅く広く”紹介。「神」と「仏」は何が違うのか、ユダヤ教・キリスト教・イスラム教の共通点など、宗教全般の歴史や世界観について、わかりやすく説く。
要約
なぜ「神」と「仏」が区別されるのか
「神」という概念はかなり広い。
日本のアマテラス、スサノヲなど、「八百万の神々」も神であるし、インドのシヴァやクリシュナも神である。イスラム教のアッラーも神と呼ばれるし、キリスト教の信仰対象も神だ。
地球上のどの民族の拝む霊的で人格的な存在も日本語では概ね神と呼ばれる。しかし、日本には仏様もいる。神社で拝むのが神様で、お寺で拝むのが仏様だ。こと仏教に関しては仏と呼ばれ、神とは呼ばれない。英語でも普通、Buddhaをgodとは呼ばない。なぜ区別するのか。
日本語の事情
第1に、日本語で「神」と「仏」が並立しているのは、ある意味で当然である。土着の神霊的存在を「カミ」と呼んでいたところに、外来宗教が「仏」という言葉と概念を持ち込んだからだ。
では、なぜキリスト教の信仰対象が、仏ではなく神の箱に放り込まれることになったのか。
中世に至るまで、土着の信仰対象であるカミは、威圧的な、恐ろしい力を意味した。雷のような自然現象とか、人間に取り憑く霊威とかである。他方、外来の仏教の仏は、人間を優しく悟りの世界へ導く救済者という意味合いをもっていた。言葉の意味合いとして、違った観念を表していたのだ。
しかし、両者は次第に接近していく。いわゆる「神仏習合」という現象を通じ、神は救済者的な性格を強くもつようになった。江戸時代末期に出現した天理教や金光教という新宗教の神様は、優しい救いの神様だ。今日、日本人が「神仏」と呼んでいるものも、そうしたイメージに近い。
このように、日本の神は仏教と長く接触していたおかげで、超越的な救いの神としての性格をもつようになった。
明治になってキリスト教の信仰対象が神と訳されるようになったのは、1つには、この言葉の意味合いがキリスト教的な概念として転用できるほど広いものになっていたためであると思われる。
では、なぜ仏という語を採用しなかったのかというと、これはまた別の事情からである。仏はBuddhaに相当する。このBuddhaを欧米人は普通godとは呼ばないのだ。それはなぜか。
「ブッダ」の起源
ここで第2の事情に話が移る。日本を離れて国際的に見ても、Buddhaとgodは一緒ではない。