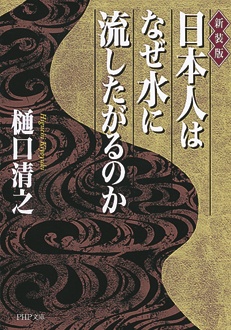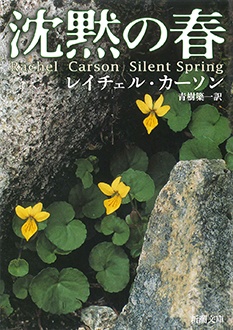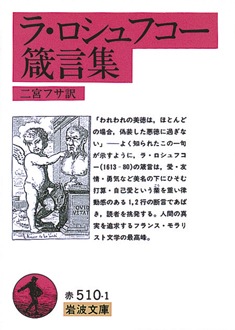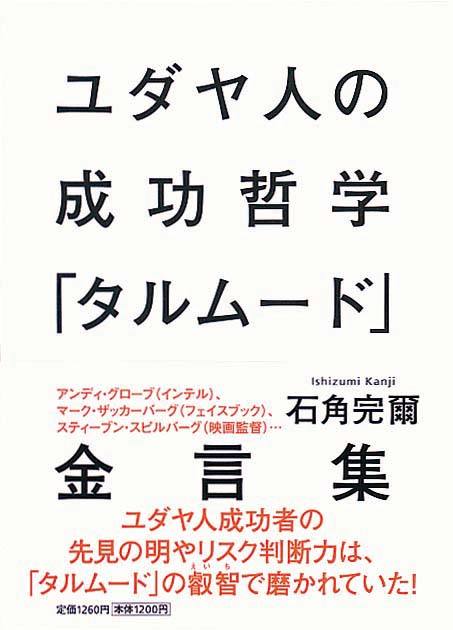2015年5月号掲載
〔新装版〕日本人はなぜ水に流したがるのか
- 著者
- 出版社
- 発行日2015年2月19日
- 定価660円
- ページ数221ページ
※『TOPPOINT』にお申し込みいただき「月刊誌会員」にご登録いただくと、ご利用いただけます。
※最新号以前に掲載の要約をご覧いただくには、別途「月刊誌プラス会員」のお申し込みが必要です。
著者紹介
概要
過ぎたことを咎めず、無かったことにする。日本人の「水に流す」行動様式は、私たちが暮らす上ではよき潤滑油となるが、国際社会では問題が多い。近隣諸国との歴史認識を巡るトラブルも、これでは解決は難しい。本書は、この日本人独特の、水に流す心情を考察したもの。“水”との歴史的、文化的関わりを軸に日本人の精神風土を探った、ユニークな文化論だ。
要約
「水に流す」心情を育んだもの
「水に流す」とは、今まであったことを、さらりと忘れ去ってしまうことである。
日本人の行動様式をみると、この「水に流す」傾向が極めて強い。善くも悪くも、過去に対してわだかまりがなく、済んでしまったことは仕方がないという気分が支配的である。
過去にこだわらず、論わず、責めず、忘れ、受容し、許す ―― この日本人の行動様式はおだやかで優しい人間関係を維持するための知恵として、また寛容な人間性の美点として歓迎されてきた。
しかし、今日のように日本が世界の中で経済大国として浮上し、我々日本人が好むと好まざるとにかかわらず、国際社会の歴史、文化、生活習慣と接触する機会が多くなる中で、この「水に流す」心情は、とかくトラブルの原因を生み出すものとして指摘されるようになってきた。
そこで、「水に流す」心情を改めて振り返り、その由来、現象、そしてその功罪を考えてみよう。
川は巨大なゴミ捨て場だった
日本人の「水に流す」性格を考えるにあたって、まず頭に浮かぶのは“川”である。
そこでまず始めに、日本人を取りまく川と自然条件をたどってみる。なぜなら、人間の性格には、その環境が与える影響が大きいからである。
川は古代から文明発祥地の中心にあった。エジプト文明のナイル川、メソポタミア文明のチグリス・ユーフラテス川、インダス文明のインダス川、中国の黄河。日本でいえば、大和時代の明日香川、京都の鴨川、江戸の隅田川ということになる。
こう書いてみると、どうも世界の大河から比べると、日本の川は小川程度の規模に見えてしまう。ライン川などのように、何カ国もまたがって流れる川とは、明らかに違う様相を呈している。
しかし、日本の川には、大きな特徴がある。流れの速い川が多いのだ。
理由の1つは、モンスーン季節風帯に属する温帯気候の国であること。そのため、年間の降水量が多く、川の水量も多くなる。