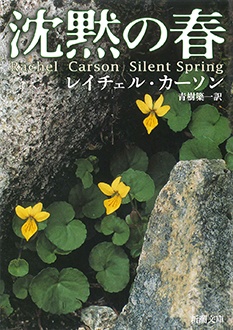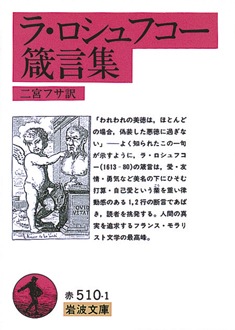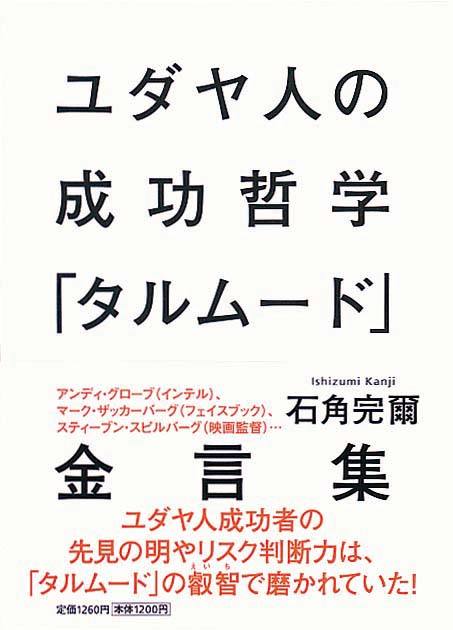2016年9月号掲載
禅がわかる本
著者紹介
概要
禅の教えは、日々の暮らしの中で活かされてこそ意味がある ―― 。そう言う著者が、禅とは何かを一般の人に向け平易に説く。「禅の悟りとは、“わからない”ことが“わからないことだとわかる”こと」など、まさに目から鱗の話がぎっしり。禅の世界が見えてくるのはもちろん、人が生きる上でのヒントに満ちあふれた1冊だ。
要約
片手の声を聞け
禅が教えようとしていること、それは、こだわりのない「自由」な精神である。
自由ということは「自分に由る」ことであって、「世間の常識に由る」ことではない。禅の世界に遊ぼうとする者は、まず最初に「常識」を蹴飛ばさねばならない。
江戸時代の禅僧である白隠禅師が、《隻手の音声》という公案(禅宗で、修行者が悟りを開くため、研究課題として与えられる問題)をつくっている。「隻手」とは片手のことであり、「片手の声を聞け!」というのが、この公案の意味である。
もちろん常識でわかることだが、両手を合わせて打ってこそ「ポン」と音が出るのであり、片手だけでは音は出ない。
では、白隠はなぜこんな公案を創案したのか?
多分、我々が「相対の世界」に生きているのに対して、そんな「相対の世界」から脱却せよと教えるために、この公案を突き付けたのだと思う。
「相対の世界」とは、例えば親子の断絶である。
親は、子どもが親の言うことを聞かないと、子どもを非難する。子どもは子どもで、親が自分を理解してくれないと嘆いている。
でも、親子は相対的であるから、親が子に歩み寄れば、2人の距離は縮まることになる。
私たちは日常生活において、相手を変えよう、相手を動かそうとしている。それもたいていは、相手を自分の都合のいいように変え、動かそうとする。それはあまりにも虫がよすぎる話である。
そうではなく、自分が変わればいいのである。自分が相手に近づいて行けば、相手は私に近づいて来ることになる。相手が自分を愛することを期待するより、自分が近づいて行った方が距離は近くなるのである。