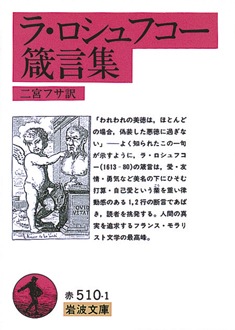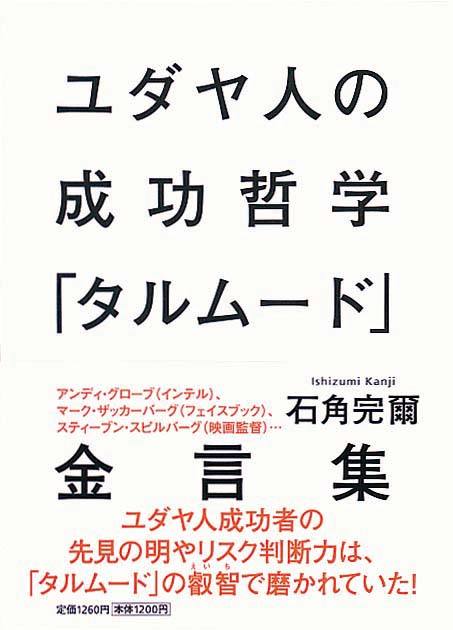2024年2月号掲載
戦争と哲学
- 著者
- 出版社
- 発行日2023年11月30日
- 定価1,199円
- ページ数229ページ
※『TOPPOINT』にお申し込みいただき「月刊誌会員」にご登録いただくと、ご利用いただけます。
※最新号以前に掲載の要約をご覧いただくには、別途「月刊誌プラス会員」のお申し込みが必要です。
著者紹介
概要
「大義のために戦う戦争と、大義を問い直して提示する哲学は、基本的に繋がっている」。こう述べる著者が、ペルシア戦争からウクライナ戦争まで、様々な戦争を取り上げ、哲学と戦争との関係性を説いた。なぜ、哲学が戦争と関わるのか。プラトン、カントといった哲学者は戦争についてどう語ったのか。歴史を辿りつつ詳説する。
要約
戦争には大義が必要
戦争というものは、どんな戦争であっても必ず“大義”があり、それを掲げて戦う。どんな侵略戦争でも、大義というものは必ずある。
一方、哲学は、そもそもの理由や原因、一番根本的なものを問い直していく学問である。この根本的な“原因”や“根拠”は、“大義”と言い換えることもできる。そうしたことから、大義のために戦う戦争と、大義を問い直して提示する哲学は基本的に繋がっていると考えられる。その意味では、「戦うべき大義を提示するのが哲学という学問の1つの活動」と言えるかもしれない。
哲学原理が戦争の大義となる
もちろん大義はすべて正しいわけではなく、誤解されることも少なくない。例えば、第二次世界大戦前の日本において、戦争教育をしたということで批判を受けた哲学の学派が、京都学派だった。
当時、ドイツの哲学者シュペングラーが書いた『西洋の没落』が大きな話題となった。それは、20世紀に入り、西洋が歴史的に1つの終わりを迎えているという発想で、それを受けて京都学派の西田幾多郎らは、西洋を東洋思想で“超克”するという対立図式を作ったのだ。
この西洋を東洋の原理で超克するという図式は、戦争の中に組み込まれていった。つまり、日本が“大東亜共栄圏”を唱え、東洋の解放という形で西洋と相対したのは、西洋哲学を東洋哲学で超克するという発想の戦争版になるわけだ。
西洋の原理を東洋の考え方で超克するという発想自体は、特に問題ではない。そうしなければ、永遠に西洋に追随することしかできなくなる。だが、この発想が現実的な戦争の中に組み込まれてしまった。つまり、大義を作ってしまったわけだ。
大義と哲学
これまでの歴史を振り返っても、様々な哲学者が戦うべき大義を提示してきた。古代ギリシャであれば“ポリス”のために。中世であれば“神”のために。近代に至れば“国や民族”のために。
それを哲学的な原理として提示することと、戦争の大義として提示することは、非常に近い関係にある。その意味では、哲学を理解するには戦争の問題も考える必要があるし、戦争の問題は哲学的な表現という形で考えていかねばならないのだ。
ウクライナ戦争を考える
ウクライナの戦争は、「先に手を出したのは誰か」で世論が決まってしまった感じはする。一般のイメージは「領土欲のプーチンVS悲劇の英雄ゼレンスキー」という構図になっていて、大義があるのはゼレンスキーのみ、というものだ。
しかし、ここで非常に大きな問題は、何をもって“先に手を出した”と言えるかということで、それによって大義も変わる可能性がある。