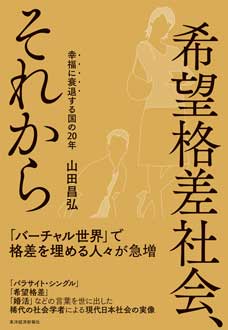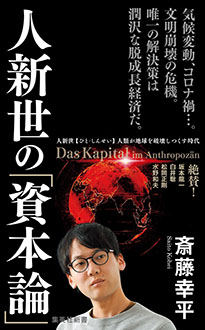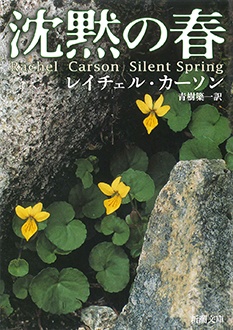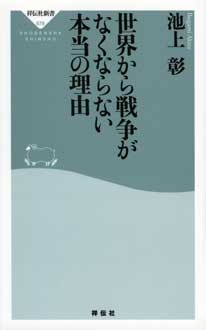2025年4月号掲載
希望格差社会、それから 幸福に衰退する国の20年
著者紹介
概要
昭和から令和の間に、日本では格差が広がった。正社員になれないまま歳を重ねる「就職氷河期世代」、親の格差が子に受け継がれる「親ガチャ」…。こうした言葉が生まれる中、活気づいているのが“バーチャル世界”だ。将来に希望が持てず、ネットゲームや推し活などリアルとは別の場で格差を埋める。そんな人々の実像を描き出す。
要約
格差社会の変遷
2022年の『令和4年版・男女共同参画白書』の中に「もはや昭和ではない」というコピーがある。
このコピーには、昭和終了から30年以上経つにもかかわらず、いまだ日本社会は昭和の呪縛にとらわれている、という含意がある。では、昭和と令和の間の平成は、どのような時代だったのか。
戦後の昭和期 ―― 中流化社会
戦後から高度成長期を経て、バブル経済期までは、経済格差が個人にとってほとんど問題とならなかった時代といえる。それは、経済格差が存在しても、それを乗り越えられると思えたからだ。
戦後の復興から高度成長期に、ほとんどすべての人の生活水準が向上した。工業化が進む中、若者男性の労働力需要が旺盛で、ほとんどの男性の収入は安定し増大したからだ。また、女性は、結婚して専業主婦になっても安心して生活できた。
その結果、「夫が主に仕事、妻が主に家事育児で豊かな生活を築く」という戦後型家族モデルがほとんどの若者に形成可能だった。
平成期 ―― 格差拡大が進行
平成期のはじめに、バブル経済の崩壊(1992年頃)が起きる。それとほぼ同時に、グローバル化経済の波が日本にも押し寄せる。
IT化、産業や経済のサービス化が進行し、その結果、高度にインテリジェンスが必要な人材が求められる一方、大量の非正規雇用の需要が生じる。サービス業や製造業などで大量の流動的労働者(単純労働に従事し、必要がなくなれば解雇することが容易な労働者)が必要になったからだ。
流動的でコストが低い非正規雇用者の需要が増えれば、正社員の需要は減る。その結果、経済的に不安定な男性が増えた。
そうした若者が増えると、結婚できない男女が増加する。だから、経済的に安定した正社員としての就職を求める「就活」や、経済的に安定した結婚相手を求める「婚活」をする人が増える。
このように、就活、婚活という言葉が生まれ、就職や結婚に対するプレッシャーが強まっていったのが、平成時代の特徴といえるだろう。
希望格差社会の出現
そんな時代でも、正規雇用者であれば、社内で努力すれば昇進し、報われると思えた。正規雇用者と結婚できた女性も、家事育児で努力すれば、豊かな生活を築くという希望を持つことができた。