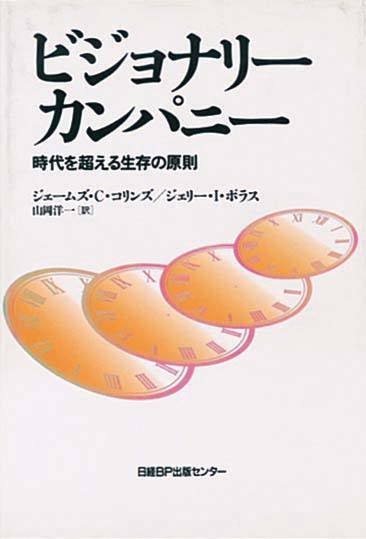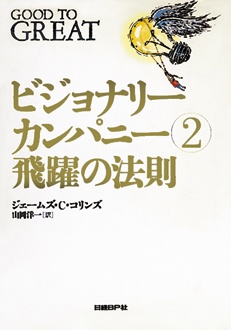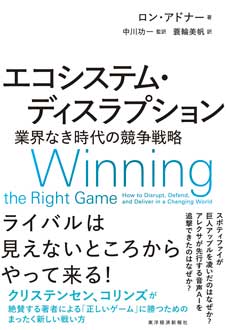2025年4月号掲載
経営は無理をせよ、無茶はするな オーバーエクステンション戦略のすすめ
- 著者
- 出版社
- 発行日2025年2月12日
- 定価2,200円
- ページ数290ページ
※『TOPPOINT』にお申し込みいただき「月刊誌会員」にご登録いただくと、ご利用いただけます。
※最新号以前に掲載の要約をご覧いただくには、別途「月刊誌プラス会員」のお申し込みが必要です。
著者紹介
概要
長年、日本企業を観察し、応援してきた著者が、日本企業復活のための「挑戦する仕組みづくり」を提案する。披露される「オーバーエクステンション戦略」は、実力不足を承知の上で、あえて新事業に挑戦することで能力を拡大する、というもの。時間や国境を超えて成立する、この成長戦略を、トヨタ自動車などを例に明快に語る。
要約
オーバーエクステンション戦略とは
「オーバーエクステンション戦略」。これは、自分に十分な実力がないことを承知の上で、あえて新しい事業活動に挑戦する戦略だ。
その挑戦の過程で、実力不足の苦しみの中で現場が学習し、その学習の結果として企業の能力基盤の大きな拡大につながる。だから、オーバーエクステンションは、多くの企業が成長の踊り場での挑戦としてとってきた戦略なのである。
世界初のハイブリッド車 ―― トヨタプリウス
例えば、プリウスの開発。エンジンとモーターを1台のクルマに搭載して必要に応じて使い分ける、ハイブリッド方式のパワートレイン(自動車の駆動機構)を持つ、この世界初の量産車をトヨタが発売したのは、1997年12月だ。同じ月に京都で開かれた国連の地球温暖化防止会議を意識したタイミングで、燃費がそれまでのクルマの2倍ほどいいという大型の製品イノベーションだった。
プリウスは、モーターを使った電気の動力源で走る自動車の時代を切り開いた最初の例となった。その成功は、歴史的意義も、トヨタ自動車という企業にとっての意義も巨大だ。しかし、プリウス開発は、自動車会社の新車開発の常識からかけ離れたオーバーエクステンションだった。
未知のパワートレイン、土地勘のない技術
まず、エンジンとモーターを使い分ける総合制御機構の開発が問題だった。誰も挑戦したことがなく、わからないことも多い。運転者が踏むアクセルとブレーキとその時のクルマの速度に応じて、どのタイミングでエンジンを回し、どのタイミングでモーターを回すか。そんな制御ソフトは、誰もつくったことがない。
しかも、開発の際の多くの難題は、電池、モーターなど、これまでは外部に主に依存していた電気部品関係の技術開発だった。つまり、トヨタにとって土地勘のない技術分野での新技術開発というオーバーエクステンションだった。
それでも、パワートレインの心臓部をハイブリッドが担う以上、それらの電気部品はクルマの主要部品という位置づけに変わる。それならば、内製するしかないとトヨタの生産部門は決意した。
超短期開発
さらに、こうした未知の生産準備を、わずか1年7カ月という超短期でやらざるを得なかった。これは、2度にわたるトヨタのトップマネジメントによるスケジュールの繰り上げがあったためだ。
2回目の繰り上げ指示の時、最初の試作車がやっと動いたばかりだった。少し進んで止まる。そんな状況で繰り上げをトップが決断した最大の理由は、ハイブリッド車開発成功を世界へ向けて発信できることのインパクトの大きさだろう。売上金額や利益ではなく、こうした開発ができる技術蓄積を社会に発信すること自体が大切だったのだ。
この目論見は、見事に成功した。日本市場で環境問題に意識の高い顧客の需要を獲得できた。オーバーエクステンションのインパクトへの信念が、プリウスを成功させ、トヨタに大きな技術蓄積を可能にしたのだ。