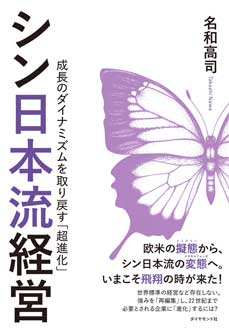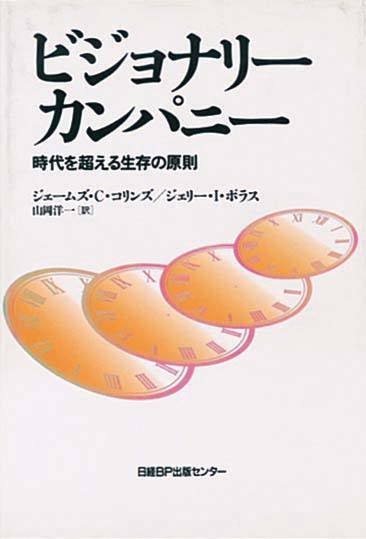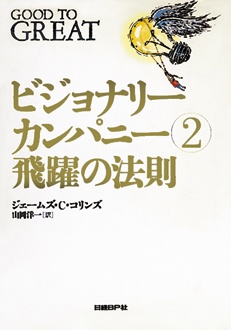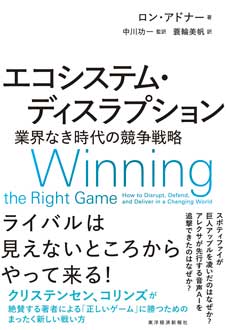2025年5月号掲載
シン日本流経営 成長のダイナミズムを取り戻す「超進化」
著者紹介
概要
日本が、「失われたX年」から抜け出すために必要なもの。それは、日本流経営のアップデートだ! 日本企業ならではの“本”は残しつつ、1つのことを「深」め、「新」しいことに挑み、「進」化する。そんな「シン」日本流の可能性を、企業事例を交え説く。自社の強みを見直し、未来へ飛翔するためのヒントが得られるだろう。
要約
分岐点に立つ日本
戦後、日本は世界が目を見張る成長を遂げた。1955~73年の約20年、実質経済成長率は10%前後の高い水準で推移した。一方、現在の日本の実質GDP成長率は2%を切る。
今後、我々の前にはどのような道が開かれているのか。それは、大きく3つに分岐している。
第1の道 ―― 超成長
第1の道は、「超成長」路線である。かつての栄光を夢見て、再成長に舵を切ろうというものだ。
日本経済が成熟という名の衰退に30年間陥り続けてきた中で、指数関数的な成長を遂げてきた日本企業は一握りだが存在する。
そうした企業では、創業者自らが「スケールアップ」を力強く牽引してきた。裏を返すと、その他の多くの残念な日本企業は、経営者の能力と覚悟において、大きく劣後していたといえそうだ。
いま日本では、働き方改革やリスキリングがブームになっている。しかし、まずは経営者自身の不退転の覚悟がない限り、通り一遍の改革の中から指数関数的な成長企業は生まれないだろう。
第2の道 ―― 脱成長
2つ目は、「脱成長」に向かう道だ。
例えば、公共政策を専門とする京都大学の広井良典教授は、「定常型社会」への移行を提唱する。
定常型社会とは、右肩上がりの成長、特に経済成長を絶対的な目標としなくとも、十分な豊かさが実現されていく社会を指す。
しかし「定常」は簡単には実現しない。生物は一見同じ状態を保っているようでも、細胞レベルでは常に入れ替わっている。定常の本質は変化しないことではなく、変化が常態化することなのだ。
定常型社会を実現するには、参加者が必死で生き抜く努力を続けなければならない。それはそれで、決して楽な選択肢ではないはずだ。