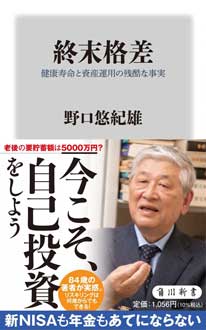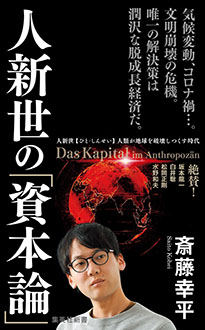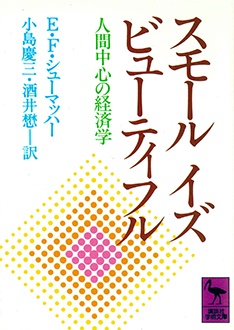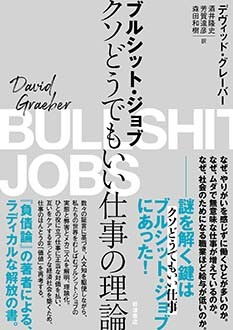2025年5月号掲載
終末格差 健康寿命と資産運用の残酷な事実
- 著者
- 出版社
- 発行日2025年2月10日
- 定価1,056円
- ページ数266ページ
※『TOPPOINT』にお申し込みいただき「月刊誌会員」にご登録いただくと、ご利用いただけます。
※最新号以前に掲載の要約をご覧いただくには、別途「月刊誌プラス会員」のお申し込みが必要です。
著者紹介
概要
2019年、「老後資金2000万円問題」が大きな議論を呼んだ。だが、少子高齢化が進む今日、本当にこの金額で十分なのか。老後生活に向けて何をどう備えるべきか。野口悠紀雄氏が、将来の国の姿を念頭に置きつつ考察した。超高齢化社会となった日本で広がる「終末格差」、年金制度が抱える問題などを、経済的な視点から論じる。
要約
団塊ジュニア世代が直面する老後問題
かつての日本では、終末の迎え方について、大きな個人差はなかった。理由の1つは、平均寿命が短かったことだ。
ところが、この数十年の間に日本人の平均寿命が延びた。今では、高齢者の介護などが大きな問題となっている。介護施設に入るにも、満足のできる民間の施設に入るには大変な費用がかかる。その費用を払える人もいるが、払えない人も多い。
こうして、終末に至るまでの状況が、人によって大きく異なるようになった。つまり、「終末格差」が広がったのだ ―― 。
団塊ジュニア世代による高齢化社会へ
これまでの少子高齢化問題の中心は「団塊世代」(1947~49年に生まれた世代)だった。人口数が非常に多いこの世代が高齢化したことで、日本は世界でも稀に見る超高齢化社会になった。
ところが、未来における高齢者問題は「団塊ジュニア世代」(1971~74年頃に生まれた世代)が中心になる。2024年では50~53歳程度になる。
団塊ジュニア世代に関連する概念として「就職氷河期」(1993~2004年頃)がある。
彼らが大学を卒業した時期は、就職氷河期と重なる。この間は有効求人倍率が1を下回っていたため、多くの人が正社員になる機会を逸した。
この世代の人々には非正規雇用が多いので、社会保障制度で守られていない場合が多い。また、非正規の場合は退職金も期待できない。だから、老後の生活資金を自分で蓄える必要がある。しかし、実際には、所得水準が低かったので資産も蓄積していない人が多い。
賃金低下とリストラに喘ぐ50代社員
日本企業では、「年功序列・終身雇用」と呼ばれる雇用体制が今でも続いているとされる。しかし、状況は変化している。50歳代の中頃になると、雇用条件が悪化する。リストラにさらされた、給料が激減したといった話はいくつもある。
こうしたこと自体は、今に始まったことではない。1970年代にも同様の傾向が見られた。「日本の賃金体系は年功序列的」と言われるが、ピークは意外に早い年齢で生じる形になっていたのだ。
ただし、2000年代以降に重要な変化があった。その1つは、賃金が伸び悩み、50歳代においてそれが顕著に見られるようになったことだ。50歳代中頃の賃金のピーク値が、絶対的にも、また若年層との比較でも低下しているのである。