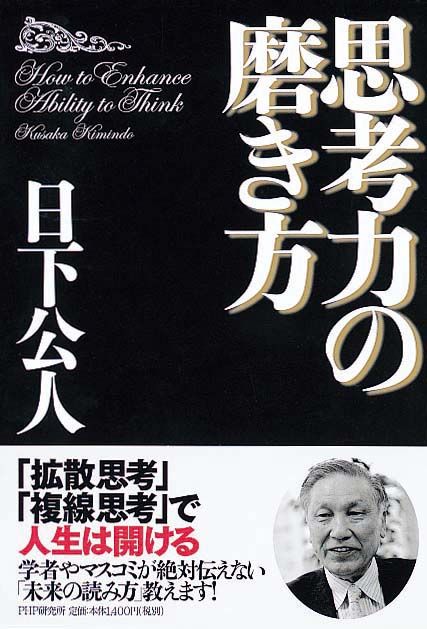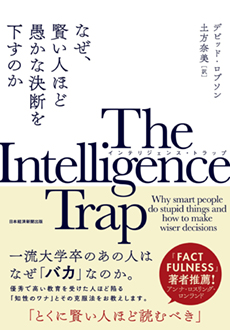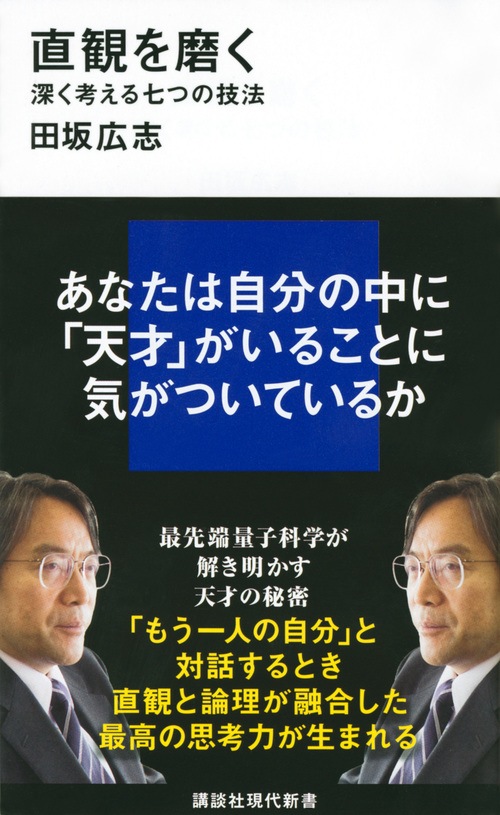2012年6月号掲載
思考力の磨き方
著者紹介
概要
政治や経済などについて語る時、ついマスコミの意見の受け売りをしてしまう…。これは、「思考力」が衰えてきた証拠。本書では、評論家の日下公人氏が、周囲の情報に惑わされることなく、未来を見通すための“頭の作り方”を指南する。「思い込み」を捨てる、自由に発想を広げる「拡散思考」を持つなど、考え方の幅を広げる上で有用なヒントが得られる1冊。
要約
日下流「思考力の磨き方」
時々、「日本はやがて中国や韓国に追い越される」「ギリシャのように財政破綻する」と真顔で語っている人がいる。それを見て、「この人たちは一体何を議論しているのだろうか」と思う。
そういう人たちは、新聞に書いてあることをしゃべっているだけで、自分の意見は何も言わない。それなら家に帰って新聞を読んでいればいいのであって、わざわざ他人と話す必要はない。
国会議員に「早期退職金制度」を
ある人は「財政赤字が大変だ」という。ならば、政府が抱えている道路やインフラを民間に売れば済む話で、資産売却は民間企業では常識である。
さらに、ある人は「国会議員の数が多すぎる。政治家はなかなか自分たちのクビを切りたがらない」という。これも解決は簡単で、現職議員に「この定数削減法案に賛成してください。その代わり、この次の総選挙に落選した現職には3億円の退職金をあげます」といえばよい。
民間企業の「早期退職金制度」のようなもので、「それならオレも辞めて、自由気ままに暮らしたい」と手を挙げる政治家が大勢いるかもしれない。1人の議員と利権を保つのにどれほどのカネを使っているかを考えると、1人3億円で議員のリストラができるなら、こんなに嬉しい話はない。
大蔵次官になった友人にこの話をしたら、「大蔵省は国会議員1人につき毎年100億円以上のムダなばら撒き予算をつけているから、3億円で1人いなくなってくれれば国民と国家の得は計り知れないものがある」といった。
このように様々なアイデアを考えることは簡単で、その議論をする自由もこの国にはある。にもかかわらず誰もが判で押したような話をしている。
なぜ学者はグラフばかり見るのか
日本人が自由な考えを封じられるようになったのは、皆が大学に行くようになったからだ。
大学は私たちが賢くなるための場所ではなく、大学教授を生活させるための場所である。では、その大学教授はどんなことを考えているのか。
例えば学者は、グラフが好きである。ありとあらゆるグラフや図表を作り、経済や社会の見方について客観性を強調しているが、実はそれほど確証はない。過去に起こったことを述べ、将来については思い込みを話しているだけである。
学者は「過去」を見るのが好きで、今までがそうだからこれからも同じ、という「直線思考」の考え方に固まっている。