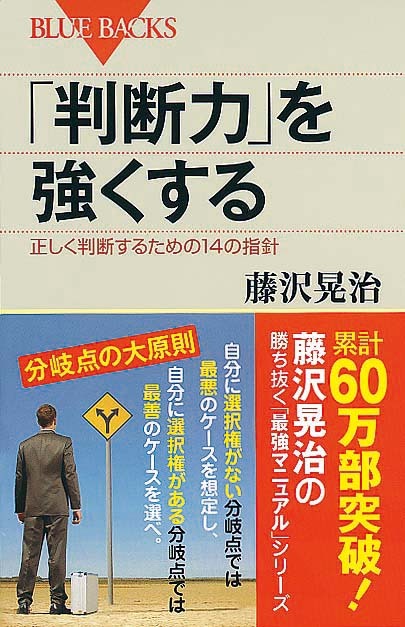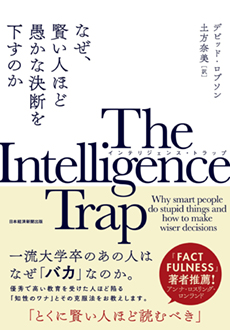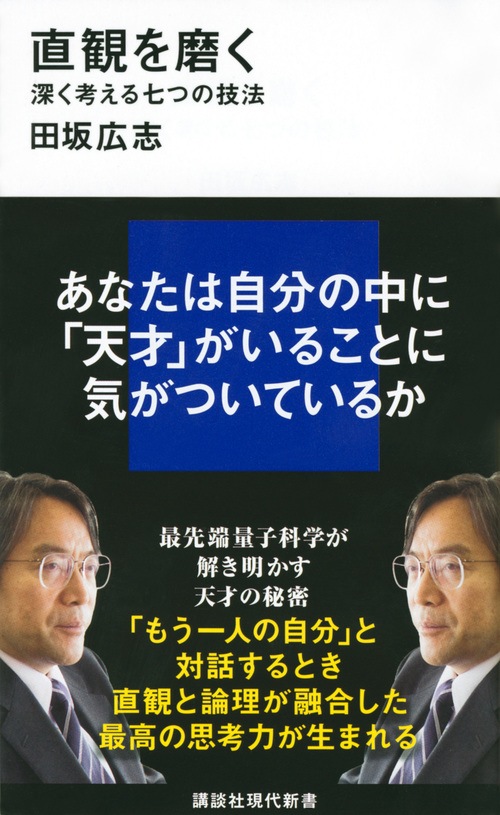2012年9月号掲載
「判断力」を強くする 正しく判断するための14の指針
- 著者
- 出版社
- 発行日2012年6月20日
- 定価880円
- ページ数177ページ
※『TOPPOINT』にお申し込みいただき「月刊誌会員」にご登録いただくと、ご利用いただけます。
※最新号以前に掲載の要約をご覧いただくには、別途「月刊誌プラス会員」のお申し込みが必要です。
著者紹介
概要
転職すべきか、家を建てるか否か、あるいは昼食を何にするか…。人は大小様々な判断を下しつつ暮らし、その中で、後で悔やむような選択をすることも多い。そうした判断ミスを防ぐのに役立つ1冊だ。「選択肢は多めに挙げよ」「最悪のケースも忘れるな」等々、正しく判断するための指針を示す他、多くの判断に使える書き込み式の「判断チャート」を紹介する。
要約
正しい判断のための指針
私たちは毎日、判断を迫られながら生活している。そして毎日、様々な判断ミスを犯してしまう。
判断を誤らないためには、次のような指針に従って判断することが重要である。
選択肢は多めに挙げよ!
不安神経症のため、5年以上も抗不安薬を飲み続けている男性がいた。だが、定年退職を機に薬に頼る生活をやめたいと思い、かかりつけの医師には内緒で薬の服用をやめた。
最初のうちは何事もなかったが、3日目あたりから強い不安に襲われた。そのため男性は「やはり薬が必要なんだ」と判断して、服用を再開した。
だが、幼なじみの外科医と飲んでいた時、「それは病気の再発じゃなくて、薬の離脱症状かもしれないよ」と言われ、別の心療内科で相談することを勧められた。
離脱症状とは、薬を急にやめた場合などに起こるリバウンド現象、いわゆる禁断症状のことだ。
早速、別の医師に相談したところ、新しい選択肢を示された。薬の服用を再開するが、3カ月ほどかけて、服用量を徐々に減らしていくのである。
こうして男性は、ついには完全に薬を断てた。
つまり、この男性が薬の服用をやめたことで不安症状が出てきた時、実は選択肢は3つあった。
-
- A:薬の元通りの服用を再開する。
- B:服用中止を続行してみる。
- C:服用を再開するが服用量を徐々に減らす。
しかし、男性は選択肢BやCには全く気づかず、すぐに選択肢Aという判断をしたのである。
判断を誤る一番の原因は、「選択肢の見落とし」だ。従って、常に「もっと別の選択肢もあるのではないか」との発想がとても大切である。