2014年5月号掲載
敗者の条件
- 著者
- 出版社
- 発行日2007年2月25日
- 定価649円
- ページ数222ページ
※『TOPPOINT』にお申し込みいただき「月刊誌会員」にご登録いただくと、ご利用いただけます。
※最新号以前に掲載の要約をご覧いただくには、別途「月刊誌プラス会員」のお申し込みが必要です。
著者紹介
概要
西洋史家の会田雄次氏が、ルネサンス時代と日本の戦国時代を考察した。戦国武将の争う世界を、欧州流の食うか食われるかの戦いの原則が支配した世界と考え、武将や君主のタイプを分析する。「一匹狼に徹しなかった者」など、示される敗者の条件には、現代に当てはまるものも。かつての闘争世界を顧みることは、今の社会の競争を理解する上でも有用といえよう。
要約
ヨーロッパ人の闘争の精神
ある日本史の学者が、私に言った。
「ヨーロッパをまわって見て変なことに気がついた。ヨーロッパの城や、中世の町の市役所を見物するとする。会議室とか食堂とか市長居室は豪壮で華やかな雰囲気に溢れている。けれど、そのすぐ隣にきまったように牢屋がある。なぜヨーロッパでは、そんなところに牢屋を置くんだ」と。
なぜ居室の隣に牢獄を置くのか
確かに、日本では自分の居室のすぐ隣に牢屋をつくるようなことはしない。なぜ、ヨーロッパでは牢獄が居室の近くに置かれたのだろうか。
ルネサンス期の支配者は、敵との死力を尽くした闘争に明け暮れた。敵を倒した時は、倒した実感にいつまでも浸っていたいと願うのが自然だ。
ナポリ王フェランテは、倒した敵の王などをバルサム漬けにして、生前と同じ服装をさせ、居間や寝室に立てておいた。寝る前に、その剥製の肩をたたいて、「ご機嫌はどうかね。俺を殺すつもりでいて、殺されたじゃないか」などとからかうためだ。
だが、剥製は所詮剥製。からかっても、怒りも恐れもしない。だから、もっとよい手は生かしておくことだ。牢に入れ、半死半生にしておくのだ。
中には憐れみを乞うのもいるだろう。罵る者もいるに違いない。だが、いかに相手が罵ろうと、その生死は完全に自分が握っている。その実感が楽しいのである。それを味わいたいという希望が、牢獄を日常生活の中へ置くことになったのだ。
厳しい自然環境が激しい闘争の精神を生む
このように激しく執拗な闘争の精神は、アメリカ人やロシア人を含む白人全部に共通するものだ。それは彼らの住む風土と歴史の産物なのである。
ヨーロッパは、冬が長く夏の日光に乏しい、やせた土地の世界である。だが、土地は平坦で、水量の多い長い河が流れ、交通に便利である。だから、いろいろの民族が続々大挙して移ってくる。激しい争いが起こらざるを得ないわけである。
土地が貧しいから生存競争に負けても山へこもるわけにはいかない。日本の昔話に、よく家を捨てて1人で山中へこもる、というようなことが出てくる。だが、ヨーロッパにそんな思想はない。山へこもったりしたら、食糧は手に入らない。わずかのどんぐり以外、山には果物も芋も何もない。
退くことは死を意味する闘争の世界 ―― それがヨーロッパである。



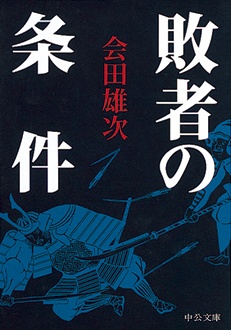










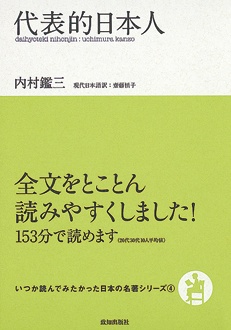
![「失敗」を研究して、そこから学ぼう [個人編]](/uploads/20200528122311-2017_5%E6%9C%88%E5%A2%97%E5%88%8A%E5%8F%B7.jpg?1603790314)

