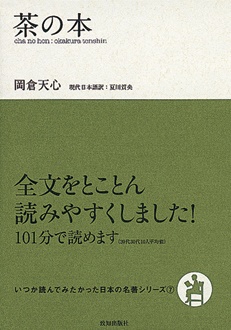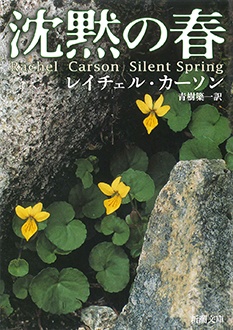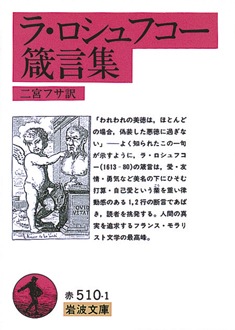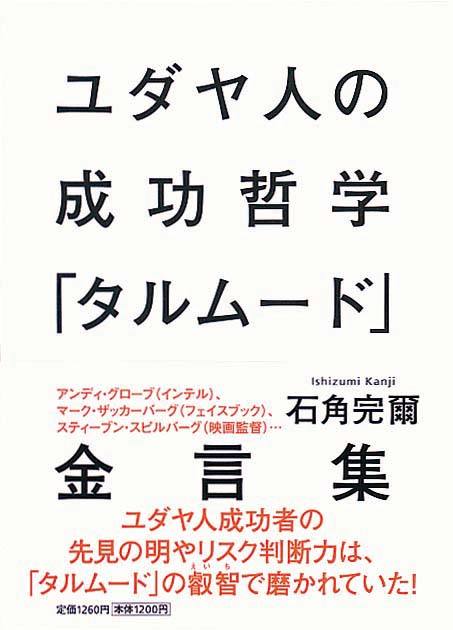2014年7月号掲載
茶の本
Original Title :THE BOOK OF TEA
著者紹介
概要
原題は「THE BOOK OF TEA」。著者は、明治期の美術界の指導者、岡倉天心。西洋と深く関わる中で、日本の素晴らしさに気づいた彼が、日本文化の象徴として見た「茶の世界」を英語で紹介した同書は、1906年に米国で出版されるや世界的なベストセラーとなった。その現代語訳である。茶を媒介に、日本人の精神、文化を説いた名著を、わかりやすく紹介する。
要約
「茶」に込められたもの
お茶は薬用から始まり、それから飲み物へ発展した。8世紀の中国において、お茶は漢詩を詠むに匹敵するほど、洗練された娯楽の1つになる。
そして15世紀の日本において、お茶は「茶道」と呼ばれる“至上の美を追求する宗教”といえるものにまで高められた。
茶道は本質的に「不完全なもの」を崇拝する。それは私たちが、「完成されないもの」と自覚しているこの人生において、それでも「実現可能な何かを成し遂げよう」と儚い試みを続ける存在だからなのである。
私たちの住居や習慣、服装や食事、陶磁器や絵画、文学までも、すべてが茶道の影響を受けている。
「単なる1杯のお茶に、何を大騒ぎしているんだろう?」 ―― 部外者から見れば、茶に関するこの大げさな話は不可思議なものに思えるだろう。
しかし考えてほしいのは、人間が生涯で享受できる楽しみの総量は、本当は小さな茶碗におさまるほど「微量なのではないか?」ということ。
そして、「その茶碗が、すぐ涙であふれてしまうのではないか?」ということ。
1杯の茶碗を重んじる精神を侮ることなど、私たちには決してできない。
茶は「その時代の精神」を映し出す
芸術と同じように、茶にも時代による個性と、流派による個性が存在する。
茶の発達は、大雑把に言えば、3つの主要な段階に分けられる。それは固形茶、抹茶(粉茶)、煎茶(葉茶)という段階。私たち現代人は、最後の流派に属しているといえるだろう。
お茶の味わい方にはいくつかの方法があり、その方法は、それぞれの時代の精神を示している。