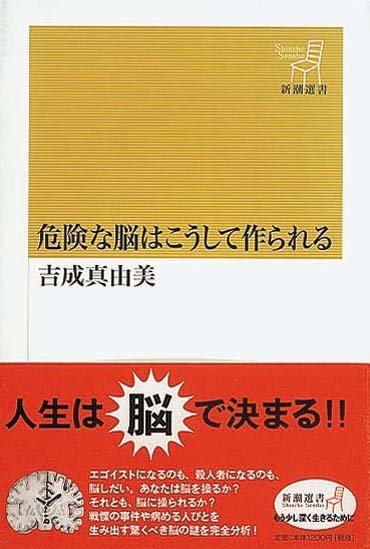2016年5月号掲載
いのちを“つくって”もいいですか? 生命科学のジレンマを考える哲学講義
著者紹介
概要
出生前診断、iPS細胞による再生医療…。近年、バイオテクノロジー(生命工学)の進歩が目覚ましい。だが、そこに規制やルールはなくていいのだろうか? 着床前診断による“産み分け”、人間の“品種改良”等々、「いのちの倫理」に関わる事例を挙げ、テクノロジーの発展がもたらす生命科学のジレンマについて考える。
要約
「理想の子ども」を選べるなら
医療の基本は、病気やけがなどで苦しんでいる人を、その苦しみから救ってあげることである。
しかし、現代の高度に発達した様々な医療技術は、「普通に機能する身体を、それ以上のものに変えていく」ことにも応用することができる。
例えば、ホルモンの異常のため身長がなかなか伸びない子どもに対して、適切なホルモン剤を投与すれば、平均的な身長に達することは可能だ。
では、「子どもを優れたバスケットボール選手にしたい」という目的で、同じホルモン剤を平均以上の身長の子どもに投与したとしたら ―― こんなことも、技術的には実現可能になっている。
医療技術のこうした使い方を、本来の目的である「治療」に対して「エンハンスメント」と呼ぶ。「強めること」「増強」という意味だ。
今、このエンハンスメントが広まりつつある。こうした傾向が進んだ先には何が待っているのか。問題はないのだろうか。
「新しい出生前診断」の広がり
妊婦のおなかの中にいる赤ちゃんに先天的な障害がないかどうかを調べる検査のことを「出生前診断」という。そして2013年から、日本でも新しいタイプの出生前診断の検査(非侵襲的出生前遺伝学的検査、NIPT)が始まった。
NIPTは、妊婦の血液(母体血)中に含まれる胎児のDNAを解析するという方法で、ダウン症などをもっているかどうかの可能性を妊娠のかなり早い時期に調べることができる。
しかし、これは妊娠している女性にとって朗報かといえば、必ずしもそうとは言えない。
NIPTが普及すると、妊婦とパートナーは「検査を受けるのか、受けないのか」、また検査の結果によっては「生むのか、生まないのか」という厳しい選択を迫られる。そして、望ましい子どもではないと判断された場合、中絶が選択される…。
でも、その子のいのちは「誰のもの」なのか。そのいのちはその子自身のものであり、親の所有物ではないはずだ。ところが、あらかじめわかってしまうことで、子どものいのちをあたかも親のものであるかのように扱い、「子どもを選別する」ことをせざるを得なくなるのだ。これは、「子どもは授かるもの」という、人のいのちの根本的な条件を崩しかねない事態ではないだろうか。