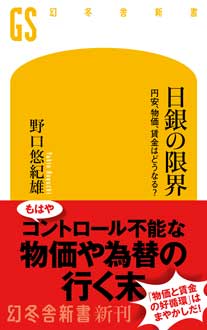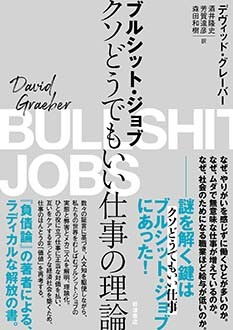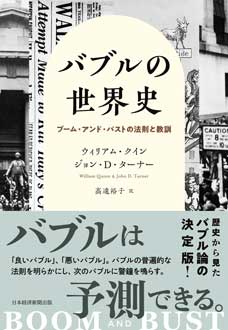2025年4月号掲載
日銀の限界 円安、物価、賃金はどうなる?
- 著者
- 出版社
- 発行日2025年1月20日
- 定価1,122円
- ページ数301ページ
※『TOPPOINT』にお申し込みいただき「月刊誌会員」にご登録いただくと、ご利用いただけます。
※最新号以前に掲載の要約をご覧いただくには、別途「月刊誌プラス会員」のお申し込みが必要です。
著者紹介
概要
日本経済の長期的な停滞は、「異常な円安」の放置によってもたらされたものだ ―― 。この国の金融政策の問題点を、野口悠紀雄氏が喝破した。諸外国にはない日本経済ならではの弱さ、そして大企業を中心に進む、インフレに便乗した「強欲資本主義」の動きなど、政府・日銀の政策運営に影響を与える諸要素を、縦横に分析する。
要約
「異常な円安」に依存した株価が大暴落
2024年7月の終わりから8月初めにかけて、株価が暴落した。それまで数年間続いていた日本経済の基調が、ここで大転換した。
それまでの基調とは、異常なまでの円安の進行と株価の上昇だ。
ドルに対して顕著に減価したのは、円だけ
日本円は、2016~19年頃までは、1ドル=105~110円程度で推移していた。ところが、アメリカが金利を引き上げた22年以降、急激に円安が進み、23年10月には150円を超える円安になった。コロナ前と比べると、円の価値は、3割以上も下落したことになる。
一方、ポンドやユーロは、22年は減価したが、その後増価し、ほぼコロナ前の水準に戻っている。日本円だけが他の主要通貨に比べて、この数年間に著しく減価したのだ。
日本だけが異常な低金利を継続
この違いを引き起こした原因は、各国の金融政策の違いだ。
例えば、FRB(連邦準備制度理事会)は、2020年3月、コロナ禍への緊急措置として政策金利をそれまでの1.75%から、歴史的低水準である0.25%にまで引き下げた。その後、22年3月からインフレ抑制のため、段階的に政策金利の引き上げが行われ、23年7月までに5.50%になった。
この他、多くの中央銀行が政策金利を大幅に引き上げた。ところが日本は、非常に低い水準を維持した。20年の政策金利はマイナス0.10%で、この水準は24年2月まで維持された。
このように、日本銀行の金融政策は、インフレ抑制を最大の課題として利上げを行ってきた諸外国とは、大きく異なるものだった。このような低金利政策が、円の国際的な価値を下落させたのだ。
株価暴落の原因
では、前述の株価暴落の原因は何か? それは「アメリカの景気指標の悪化によって、FRBの利下げ幅が大きくなり、円高が進む。それが日本企業の収益を低下させる」という予想が広がったことだ。2024年に入ってから日本企業の業績は好調だったが、それは円安によるものだったのだ。
22年頃から24年7月にかけて、顕著な円安が進み、同時に株価が目ざましく上昇した。
円安になると、なぜ株価が上昇するのか? それは、企業の利益(特に製造業の輸出関連大企業の利益)が円安で自動的に増加するからだ。