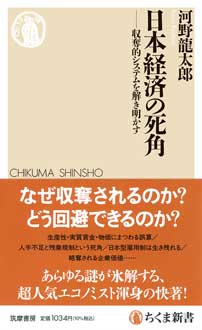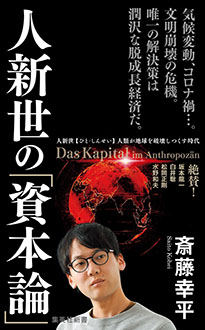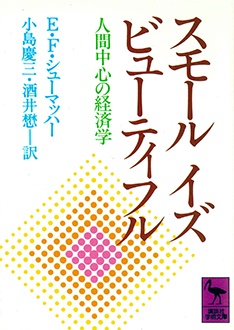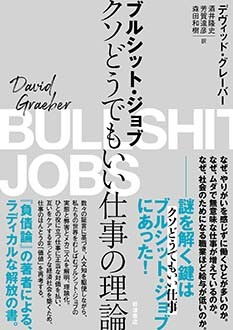2025年5月号掲載
日本経済の死角 ――収奪的システムを解き明かす
- 著者
- 出版社
- 発行日2025年2月10日
- 定価1,034円
- ページ数277ページ
※『TOPPOINT』にお申し込みいただき「月刊誌会員」にご登録いただくと、ご利用いただけます。
※最新号以前に掲載の要約をご覧いただくには、別途「月刊誌プラス会員」のお申し込みが必要です。
著者紹介
概要
日本の生産性は、この四半世紀で30%も向上した。しかし、実質賃金は横ばいのまま。なぜか? 人気エコノミストが、原因を読み解いた。儲かっても溜め込む大企業、長期雇用制を前提とした雇用慣行、株主至上主義に基づく企業統治改革…。日本経済が抱える様々な“死角” ―― 経済停滞を長期化させた要因を明確に示す。
要約
日本の実質賃金が上がらない理由
2024年9月の自民党総裁選でも、同年10月の衆議院議員総選挙でも論点だったのは、低迷する実質賃金の引き上げだった。
日本の経済エリートは、生産性を上げなければ、実質賃金を上げることはできないと論じる。しかし、日本の場合、実質賃金が上がらないのは、生産性の問題ではない。
生産性が上がっても実質賃金は横ばい
日本の時間当たりの生産性と時間当たりの実質賃金の推移を見ると、1998~2023年の間に、生産性は累計で30%ほど上昇しているが、実質賃金は横ばいのままである。
それに対し、欧州では、時間当たり生産性は、ドイツは25%程度、フランスは20%程度上昇。一方で、時間当たり実質賃金は、フランスは累計では20%弱、ドイツは15%弱と、全く増えなかった日本と違って増加している。
労働者の権利を重視する社会民主主義的な傾向の強いドイツやフランスでは、生産性が改善すると、それが実質賃金にも明確に反映されている。しかし、日本ではそれが全く反映されていない、というのが真実なのである。
儲かっても溜め込む大企業
筆者が2022年に上梓した『成長の臨界』で明らかにしたのは、日本の長期停滞の元凶が、儲かっても溜め込んで賃上げにも人的資本投資にも消極的な日本の企業、特に大企業ということだった。
1990年代末に130兆円だった利益剰余金は、2023年度は600兆円の大台に乗った。一方、過去四半世紀、(実質)賃金は横ばいだったため、近年、人件費は増えたといっても、利益剰余金の増え方に比べると、極めて限定的だ。
振り返ると、1990年代末の日本経済は、深刻な不良債権問題を抱えていた。事業会社はバブル期に過剰雇用や過剰設備、過剰債務を抱え、その後、コストカットに邁進し、支出を抑制した。
当時、過剰問題が解消されれば、企業は資金を投資に振り向け、雇用も増やすはずだと考えられていた。しかし、2000年代半ばに、不良債権問題が終息した後も、大企業は財務基盤の強化に拘り、賃上げ抑制を含め、支出抑制を続けた。
正確には、2000年代半ばには、まだ設備投資などを積極的に増やす大企業も存在した。しかし、2000年代末のリーマンショックに端を発するグローバル金融危機では、グローバル経済の急激な収縮で、一部の大企業が倒産リスクに直面した。
それ以降、万が一に備えて、儲かってもコストカットを継続し、人件費の抑制を続け、利益剰余金を積み上げる動きが加速したわけである。