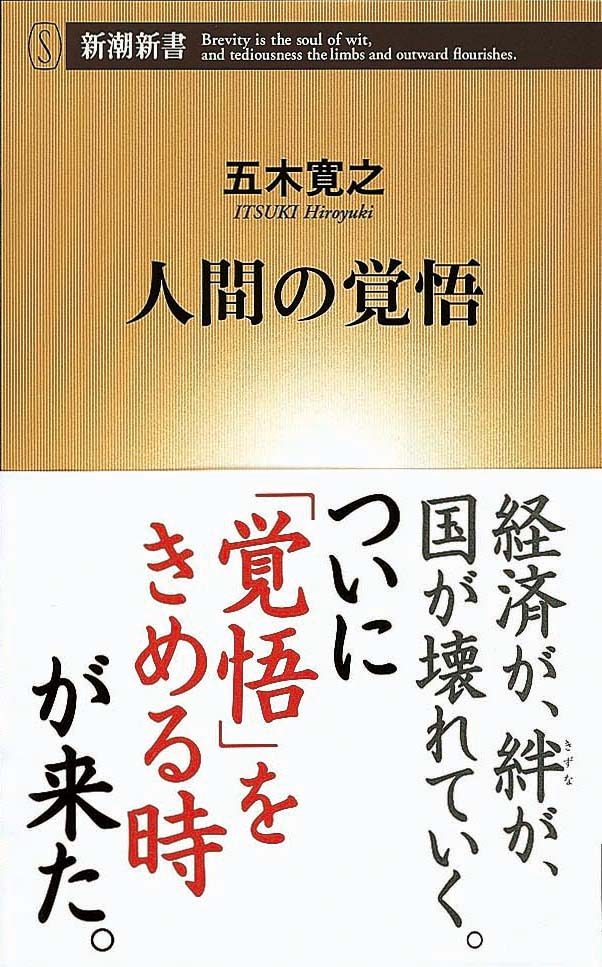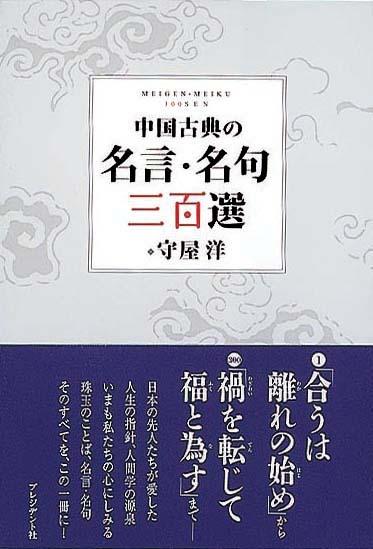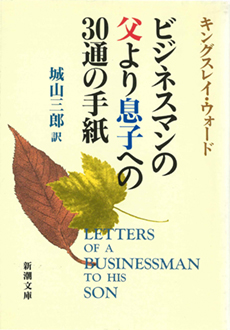2009年2月号掲載
人間の覚悟
著者紹介
概要
今、日本は漠然とした不安感に覆われている。もはや右肩上がりの経済成長は望めず、失業者は増加、自殺者も後を絶たない。この鬱々とした時代を、我々はどのように生きればよいのか? 著者は、まず「覚悟」をしなければならないと言う。現実を直視する覚悟、国にも人にも頼らない覚悟…。覚悟をすることで、暗闇の中にも一筋の光が見えてくる。
要約
覚悟するということ
そろそろ覚悟を決めなければならない。
このところ、もう躊躇している時間はない、という気がする。いよいよこの辺で覚悟するしかないな、と諦める覚悟が定まってきたのである。
「諦める」というのは、投げ出すことではない。「明らかに究める」ことだ。事実を真正面から受け止めることである。
「絶望の虚妄なることは、まさに希望と相同じい」と、魯迅は言った。絶望も希望も、共に人間の期待感である。その2つから解き放たれた目だけが、「明らかに究める」力を持つ。
希望にも絶望にも曇らされることのない目で周囲を見渡せば、驚くことばかりだ。そこで、覚悟する、という決断が必要になってくる。
私たちは無意識のうちに何かに頼って生きている。「寄らば大樹の陰」と言うが、もうそんなことを考えている段階ではない。私たちは、まさに今覚悟を決めなければならない地点に立っている。
1945年の夏、中学1年生の私は平壌(ピョンヤン)にいた。この夏、日本は戦争に敗れた。当時、日本国民の大部分は、最後まで日本が勝つと信じていた。
普通に新聞を読めば、戦局の不利は誰の目にも明らかだったはずだ。それにもかかわらず、私たちは現実をまっすぐ見る力がなかったのである。
敗戦後、ラジオは連日、「治安は維持される。日本人市民はそのまま現地にとどまるように」と、アナウンスしていた。私たちはそれを素直に受け取り、ソ連軍が進駐してくるのをただ眺めていた。
だが、敗戦の少し前から高級軍人や官僚の家族らは、平壌の駅から続々と南下していたのである。
ソ連軍の進駐後、口には出せないような事態が日本人居留民を襲い、母もその混乱の中で死んだ。