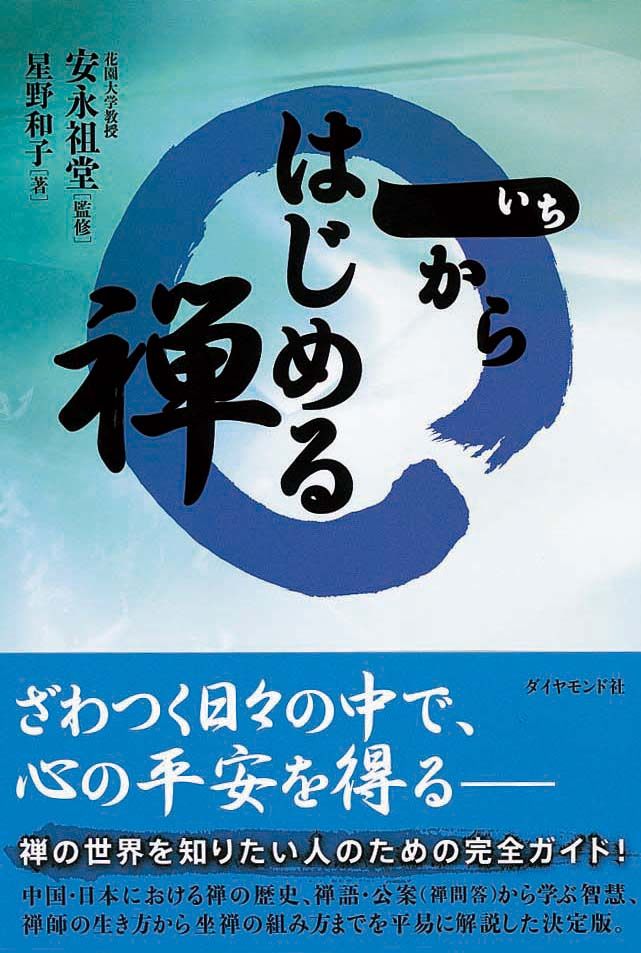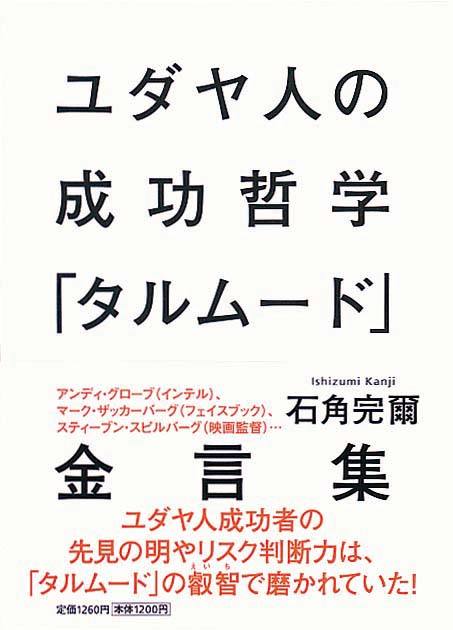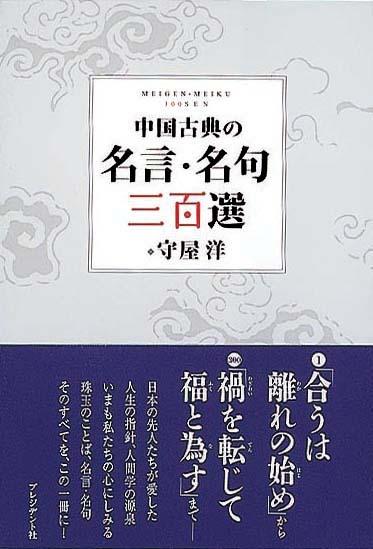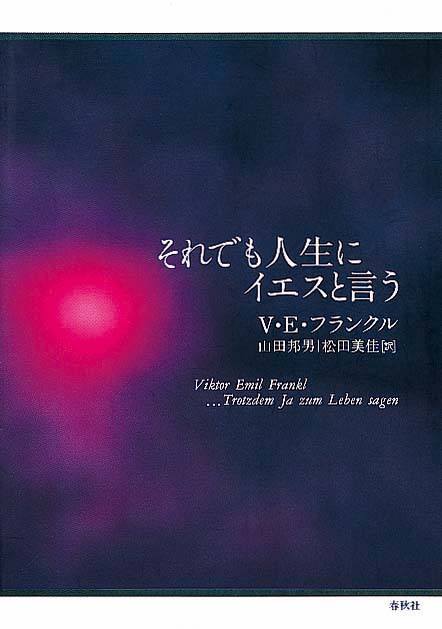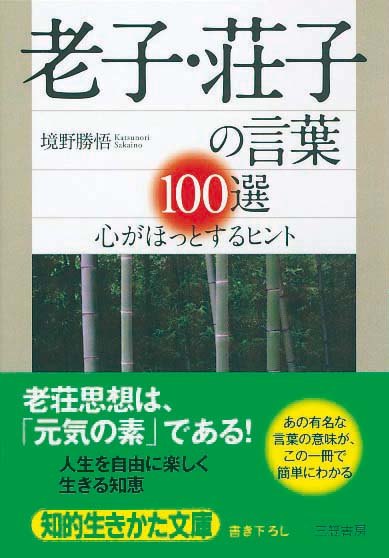2009年5月号掲載
一からはじめる禅
著者紹介
概要
今や世界の共通語となった「ZEN(禅)」。本書は、その全体像をわかりやすく解説したものである。まず、釈迦の教えに起源を持つ禅がいかに発展してきたか、歴史を概説。その上で、「只管打坐」などの禅語(禅の思想を象徴する言葉)、「隻手音声」などの公案(禅問答)を引きつつ、禅の教えの本質を示す。また、道元はじめ、主な禅師の生き方や言葉にも触れる。
要約
禅の歴史
禅の源は、釈迦が菩提樹の下で到達した悟りである。だが今、我々が禅と呼ぶものは釈迦がインドで説いた教えではなく、6世紀初頭に初祖達磨が中国に伝え、中国の地で展開した禅の思想だ。
インドで発祥した当初の禅は、あくまでも自己の完成を目指して静慮、内観する修行が中心だった。しかし中国に伝わって以降、人から人へ心(教え)を伝えることを重視するようになる。
このことは、禅が他者の成仏も願い、手助けするという性格を持つに至ったことを意味している。
初祖達磨から数えて6番目の祖師慧能の時代(7~8世紀頃)、禅はさらなる展開を見せる。
慧能は、正式な修行を経験しないまま悟りの境地を開く。つまり日常生活の中で成仏が可能であることを、身をもって示した。以後、禅では作務(勤労)を仏作仏行と重んじるようになる。
8~9世紀になると、禅は中国仏教の一大潮流となり、僧の数が増える。寺に集まり共に修行するようになったことから、禅寺の規則書が作られ、いわゆる「禅宗」と呼ばれる集団が成立した。
だがこの後、モンゴル帝国が宋を滅ぼして元を建国し、宗教統制を行ったため、禅は衰退の道をたどっていった。
そうした流れの中、禅宗にとって活路の1つになったのが日本だった。
日本の禅宗寺院では、今も炊事や掃除などの日常の作務が重要な修行と捉えられている。禅が、日本では脈々と生き続けているのである。
禅語から読み解く禅の教え
禅の思想や教え。それを象徴的に表したものが、「禅語」と呼ばれる言葉である。