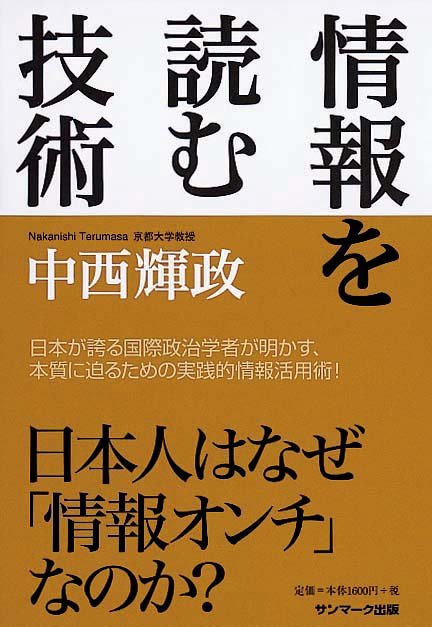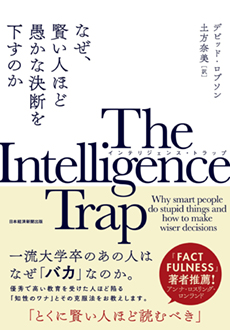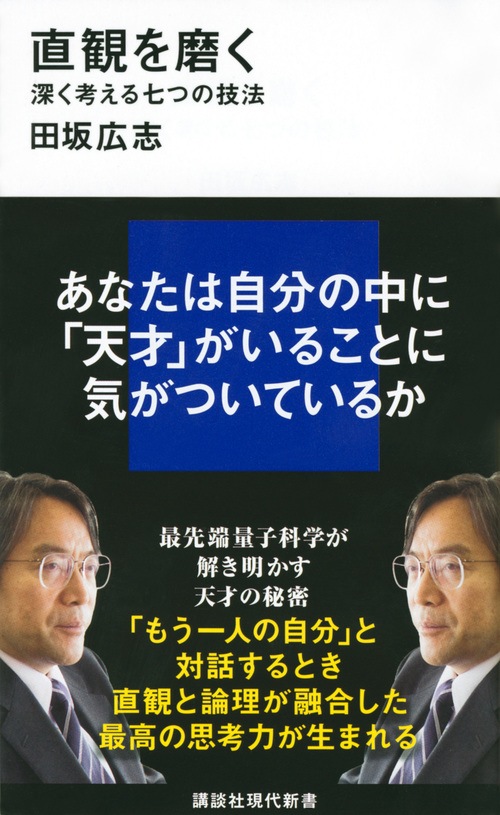2011年4月号掲載
情報を読む技術
著者紹介
概要
21世紀の今日、世の中は各種メディアの“情報”で溢れている。それらをどう読み、活用すべきかを、国際政治学者の中西輝政氏が指南した書である。「わかりやすい情報には飛びつかず、根気よく物事を考えることが必要である」「情報を取るのは早い方がいいが、それを基に決断するのは急がない方がよい」など、物事の本質に迫るための留意点が具体的に示される。
要約
本質に迫るための情報活用術
考えてみれば、戦後の日本は、本当に「いい時代」だった。
世界で重大な問題が起こっても、全て米国に任せておけば安心で、政府や経済界は右肩上がりの成長を当然のこととしていられた。国民も、終身雇用や年金を当てにした人生設計が成り立った。
だが、もはや国や企業頼みの人生設計は成り立たない。「昨日の常識は、今日の非常識」ということになる今の時代、以前のように「周りの人も皆、そう言っている」といった情報感覚では負け組となる。
こうした時代に大切なのは、「自前の情報力」を身につけること。情報に接する時は、例えば、次のようなことに留意する必要がある。
「タダほど怖いものはない」
インターネット空間には、タダで情報を提供するサイトがある。だが、タダの情報は誤りが多い。利用者をある方向に誘導しようとするものもある。
無防備な日本では、常に各国の情報工作が入り乱れている。タダで公開されているデータは、一見、客観的に見えても、かなりの嘘や意図的な情報が入っていることを承知の上で使うべきだ。
米国では、ハッカー攻撃よりも「嘘サイト」の脅威の方が恐ろしいとされ、ホワイトハウスにはそれをどう防ぐかというチームまでできている。
相手の「育ち」を調べる
小泉元首相の人気はいまだ衰えない。だが、彼が有能な政治家か、となると多くの疑問符がつく。
例えば、彼の得意分野は福祉と郵政ぐらいしかない。安全保障や教育の問題、経済政策などにおいて、彼の見識らしいものは見当たらない。
その理由は、彼の「育ち」を見れば明らかだ。
小泉家にとって政治家は「家業」なのだ。従って、自分が「政治的」であるか否かなどということは、考えるまでもないことだったのだろう。