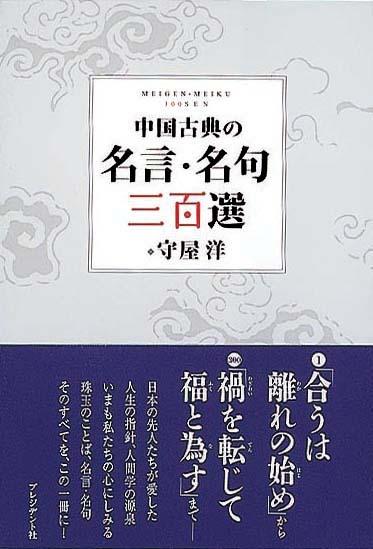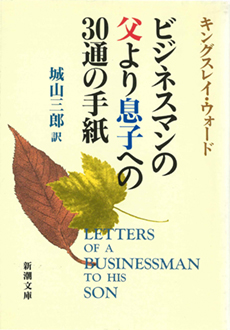2013年3月号掲載
無所属の時間で生きる
著者紹介
概要
『落日燃ゆ』や『毎日が日曜日』など、多彩な作品で知られる作家、城山三郎氏の「無所属の時間」を巡るエッセイ集。どこにも属さない1人の人間としての時間 ―― 無所属の時間をどのように過ごせば、生を充実させられるかを綴る。含蓄に富む各種のエピソードから、「ああ、この日も生きた」という満たされた思いで暮らすためのヒントが浮かび上がってくる。
要約
日帰りの悔い
某月某日、日帰りで京都へ。
余儀ない事情があり、にが手の講演だが、腰を上げた。会場のホテルへは早目に着いた。打ち合わせを済ませてからも小一時間ほどあった。その間、とくに何をするというわけでなく、窓に寄って立ち、霧の流れる東山の木立をただ眺めていた。
淡い旅情。短いが、非日常の時間。あらゆるものから、解き放されている。その思いを味わいながら、悔いも湧いた。なぜ、小一時間でなく、半日なり1日なり、こうした時間を持てるようにしなかったのか、と。
戦後最大の財界人石坂泰三を調べていて、幾日か出張するとき、空白の1日を日程に組みこんでいることに、私は注目した。
旅先で好奇心の湧いた場所や人を訪ねるためもあるが、ただ風景の中に浸っていたり、街や浜辺を散歩したり。経団連会長や万博会長など、日本でいちばん忙しい男であるはずの時期でも、そうであった。
その空白の1日、石坂は200とか300とかの肩書をふるい落とし、どこにも関係のない、どこにも属さない1人の人間として過ごした。私はそれを『もう、きみには頼まない』の中で、「無所属の時間」と呼び、その時間の大切さを、私なりに確認したつもりでいたのに ―― 。
石坂さんの例を担ぎ出すまでもない。ふだん縁のない町へ出かけ、交通機関の乱れや先方の都合などで、ぽっと時間が空いたときには、何か思わぬ拾い物をした気がする。
そこには、真新しい時間、いつもとちがうみずみずしい時間がある。おそらく、それが人間をよみがえらせるきっかけの時間となるからであろう。
不幸なことだが、入院生活にもそれに似た部分がある。というのも、大蔵次官から国鉄総裁をつとめた高木文雄から、こんな話を聞いたことがある。
「大病をして入院、役所を離れ、ただの1人の病人になってみて、世の中や人間がはじめて身近なものとして見えてきましたよ」
大病すれば即脱落と思われるほど競争のはげしい同省で、そういえば、異色の次官といわれた谷村裕も、一眼の視力を失うという大病を経験し、同省出身で大物政治家となった池田勇人や前尾繁三郎も、奇病や大病で長期間にわたり強制された余暇というか、無所属の時間を過ごしている。