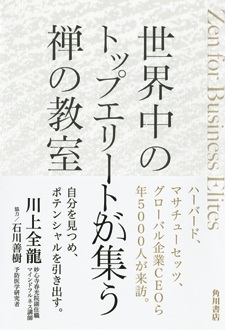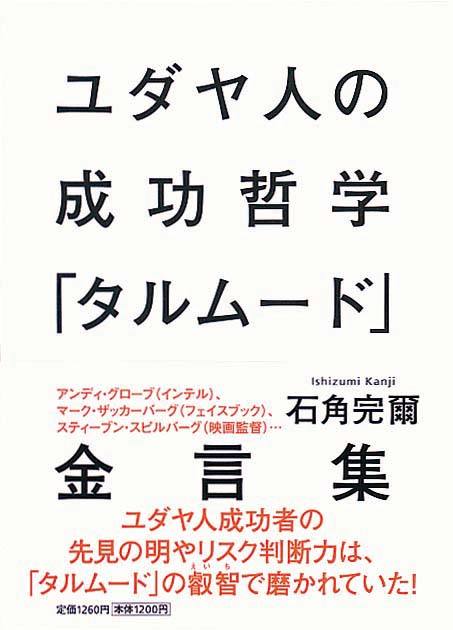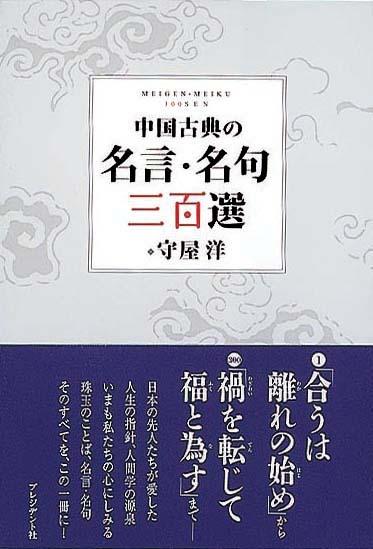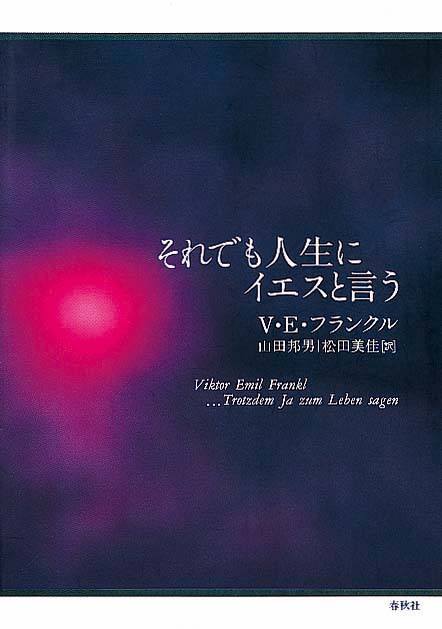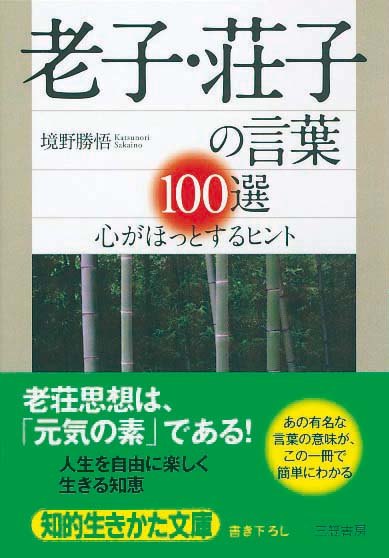2016年6月号掲載
世界中のトップエリートが集う禅の教室
著者紹介
概要
世界中から年間5000人が訪れる禅寺・春光院。そこで禅を教える僧侶が、禅の考え方や座禅の方法・効用を、最先端の科学的知見を交えつつ説く。自分を見つめ、ポテンシャルを引き出す。グローバル企業のCEOや、ハーバード、スタンフォードなど名門大学のビジネススクールに通う学生らも学んだ、禅の叡智が明かされる。
要約
トップエリートが禅に取り組む時代
世界的に成功している経営者の中には、禅や瞑想を学んだり実践したりしている人が多い。
世界のトップエリートたちはなぜ今、禅や座禅に興味を持つのか。その背景にあるのは、「マインドフルネス」というものの世界的な流行である。
心を調えるマインドフルネス
マインドフルネスとは、その提唱者であるジョン・カバット・ジン博士の定義では、「今ここでの経験に、評価や判断を加えることなく、能動的に注意を向けること」である。
概して、自分の内面で起こっていることに気づき、それを客観的に見つめ直すことで心のコンディションを調え、より自制心や創造性を発揮しやすい状態を作るエクササイズのことを同時に指す。とりわけ仏教、中でも禅宗の瞑想を、最新の脳科学の知見などを踏まえて現代に合うように作り直した瞑想のトレーニングのことを言う。
その背景には1990年代以降に、脳科学や心理学の研究により、瞑想が自己や状況の客観的な思考、自制心、継続力や、他者への共感力の涵養に役立つことが明らかにされてきたことがある。
西洋人が注目しはじめた東洋的な考え
そして、マインドフルネスの根源にある東洋的、仏教的な思想も重要なものとして注目を浴びはじめている。その背景には、西洋的な価値観に対する行き詰まりが生まれたことがある。
今までの西洋世界は、勤労主義を重視し、自分を苦しめてでも努力することを美徳とした。プレッシャーに耐え、懸命に努力してこそ何かが摑めるのだというものだ。これはキリスト教、特にプロテスタント的な考え方に親和性がある。
これまでの西洋近代的な社会を動かしてきたもう1つの考え方は、実践主義(プラグマティズム)である。世の中の事象を有益か否かに分け、実利を突き詰めることが善であるという考え方だ。
だが2008年のリーマン・ショックで、その実践主義が壁にぶち当たった。以来、何か違う考え方が必要なのではないかと思う欧米人が増えた。そして、自分たちとは違う思想や文化に目を向けるようになり、仏教的な考え方、東洋的な思想も重要ではないかと考える人たちも生まれたのだ。
金融危機を経て世界は新しい価値観を求めている
米国では、リーマン・ショックについて、ファイナンシャル・メルトダウンという表現が使われる。つまり、あの出来事は、金融中心の資本主義社会が融解して底が抜けた感覚を強く米国人に印象付けた。それまでずっと資本主義を駆動してきた勤労主義と実践主義が、機能しなくなりつつあるという認識が広がっている。
もう1つ、近代の西洋社会で強く叫ばれてきた言葉に「自己実現」がある。これは、自分のゴールに向かって、自分をどれだけ高められるかということであり、結局は自己中心的な考え方だ。