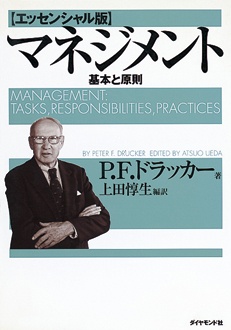2019年10月号掲載
野生化するイノベーション 日本経済「失われた20年」を超える
著者紹介
概要
イノベーションを、「野生化」=ヒト・モノ・カネの流動化の観点から考察したものだ。イノベーションを組織内で管理すると、アイデアが色褪せる。流動性が高まるとイノベーションが生まれやすいが、失業者の増加や格差の拡大など、破壊的な側面も強まるという。イノベーションの今を知り、これからを考える上で示唆に富む書。
要約
イノベーションはマネジメントできるか
イノベーションが「野生化」している。
イノベーションは生物ではなく人工物なので、もちろんこれはメタファー(隠喩)である。
野生化。このメタファーを使って光を当てたいのは、イノベーションは人間のコントロールを超えて、あたかも生きているかのようにビジネス・チャンスに向かって動き出すという側面だ ―― 。
野生的だったイノベーション
歴史的に見ると、イノベーションは必ずしも組織的に生み出されてきたわけではない。産業革命を牽引したのは、個人の発明家や企業家だ。彼らは、自分で蒸気機関や紡績機をつくった。元来、イノベーションは極めて野生的な存在だったのだ。
しかし、その後、徐々にイノベーションの発生の仕方が変わっていく。生産に使う機械が高度化し、価格が上がったため、大きな資金調達が必要になる。生産設備に投下した資金を効率よく回収するには、大量に生産することが大切になる。
それらのマネジメントは、発明家や企業家が1人でできるものではない。組織的にきちんと管理しなければならない。つまり、極めて野生的な存在であったイノベーションを飼いならすために、「企業」という存在が必要とされたのである。
研究開発を内部化する
20世紀に入ると、米国で原材料の調達から生産、販売までを自社で行う、いわゆる垂直統合の程度の高い大企業が出てきた。
そして多くの経営資源を内部化した企業、特に研究開発機能を内部化した企業は、それらを効率的にマネジメントしてイノベーションを生み出そうとした。個人の発明家や企業家が生み出してきたイノベーションのタネを、企業の内部で生み出そうとし始めたのだ。つまり、イノベーションをマネジメント(管理)しようとしたわけだ。
セレンディピティとマネジメント
だが、なかなか成果が出なかった。なぜか?
それを考える上で、細菌学者のアレクサンダー・フレミングの事例が参考になる。
フレミングは、リゾチームとペニシリンの2つの抗生物質を発見した。この偉大な発見は、偶然の要素が大きかった。リゾチームは、彼が細菌を塗抹したシャーレの上でくしゃみをし、それが放置されていたことで発見された。ペニシリンは、ブドウ球菌を培養中のシャーレに、偶然、カビの胞子が落ち、カビの周りのブドウ球菌が溶解していることをフレミングが発見したのだ。