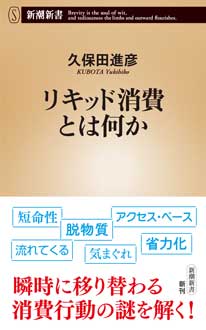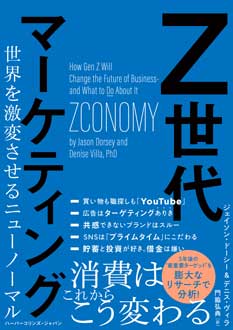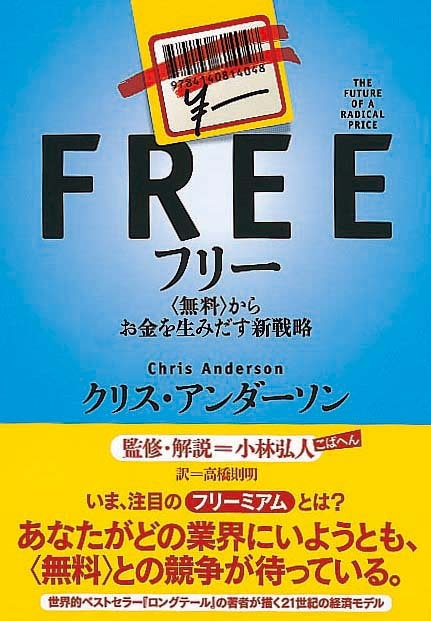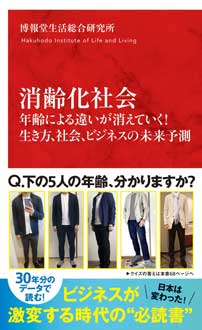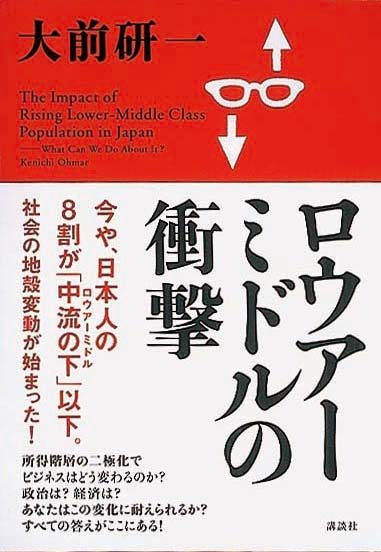2025年5月号掲載
リキッド消費とは何か
著者紹介
概要
その時々で欲しいものが変わる、買わなくてもレンタルやシェアリングでOK、物より経験の方が大切…。現代人の消費行動は「欲しいものを購入し所有する」という従来の姿から大きく変化した。そこにはどんな心理が働いているのか。この謎を解くカギとなる「リキッド消費」という概念について、マーケティングの専門家が論じる。
要約
消費が液状化する
今日、私たちの消費生活は大きく変化している。その変化を捉えたものに、「リキッド消費(液状化した消費)」というコンセプトがある。
リキッド消費の3つの特徴
この概念は、バーディーとエカートというイギリスの研究者によって2017年に提唱された。彼女らは、リキッド消費を「短命で、アクセス・ベースで、脱物質的なもの」と定義している。
①価値のはかなさ「短命性」
短命性とは、「価値が文脈特定的」となり、その寿命が短くなることである。
「価値が文脈特定的となる」とは、おおまかには「価値が場面ごとに限定される」と考えてよい。現代人の生活は、仕事、家庭、友人関係など、複数の場面から構成されている。多くの人は、それぞれの場面に応じて複数の顔を持っており、価値観も場面ごとに変化する。
価値が文脈特定的になれば、消費行動もそれに応じて変化する。その場に応じて次から次へと楽しむ消費をイメージするとわかりやすい。この傾向が強まると、価値の寿命は短くなり、個々の製品やサービスの陳腐化も早まる。
②所有しないで消費する「アクセス・ベース」
アクセス・ベース消費とは、「所有権の移転が生じない取引によって構成される消費」のこと。つまり物を購入して所有するのではなく、一時的にアクセスして経験を得る消費のことだ。
アクセス・ベース消費はレンタル、リース、シェアリングなどによって実現される。最近では特にコンテンツ・ビジネスの多く、例えば音楽や動画の配信がアクセス・ベースになりつつある。
③ものに頼らない「脱物質」
脱物質とは、同じ水準の機能や価値を得るために、物質をより少なくしか使用しないことである。
例えば、かつて私たちは、ネガやプリントという物質の状態で写真を保有していた。しかし今では、大半の人がスマートフォンやパソコンの中にデジタル・データとして保有している。
消費における脱物質化は、非物質的な財(サービス財や情報財)が増加したことに加えて、消費者自身がものよりも経験を重視する傾向が強まったことでも、加速している。
バーディーとエカートは、現代のステータス・シグナルが「目立たないこと」「経験を含む非所有」「知識と職人技に基づく本物」に依存しつつあると指摘している。贅沢で排他的な高級ブランドを所有することよりも、ユニークな冒険旅行をしたり、芸術的な体験をしたりすることの方が、人々の羨望や喝采を浴びるというわけだ。