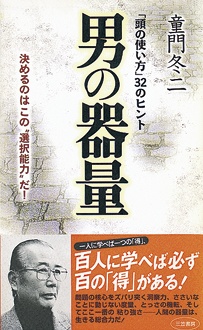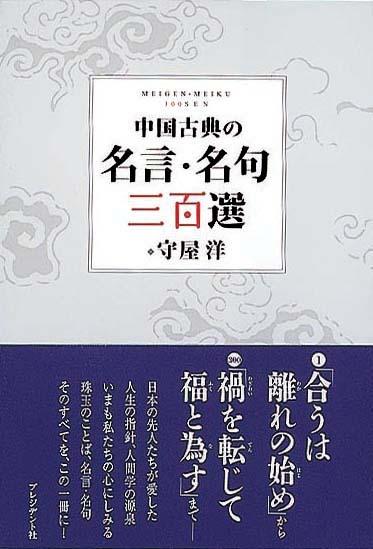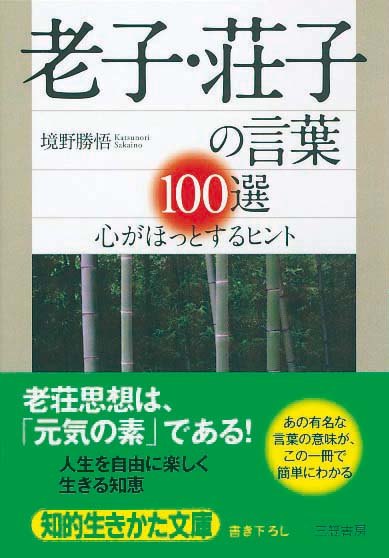2001年1月号掲載
男の器量 「頭の使い方」32のヒント
著者紹介
概要
醜態をさらす指導者の多い昨今、「男の生きざま」が改めて問われている。本書は、「自分の原則」を持ち、その原則に基づく生きざまを貫いた歴史上の人物のエピソードを紹介する。それらエピソードを通じて描き出される、彼らの人間としての「器量」の大きさは、現代に生きる我々も大いに学ぶべきものである。
要約
「生きざま」を貫いた人々
現代は、「自己表現(パフォーマンス)の時代だ」という。そのため、「ヒトから視られている」という意識が前面に出ている時代である。が、それだけに「視られること」を意識した言動がミエミエになり、多くの良識人を白けさせている。
勢い、人間の原点に立脚する「生きざま」に郷愁を覚えることになるのだが、歴史上の人物にも「自分の原則」を持ち、損得を超えて生きざまを貫いた様々な人々がいる。例えば ――
不遇が人の器量を育てる!
加賀百万石の祖・前田利家は、若い頃しばしば主人である織田信長や豊臣秀吉の勘気を被って退けられ、「不遇の状況」に陥った。
これは利家の「正義感と表現のズレ」に起因している。彼は極めて強い正義感を持っていたが、表現力が乏しかった。少ない言葉であふれる正義感を表現するものだから、つい激しい言葉になる。そのため、周囲から反感を買うのだ。
だが、利家はそんな不遇の時代から多くを学んでいる。例えば、友人の分析である。
自分が信長に退けられてから「全く訪ねてこなくなった者」と「相変わらず訪ねてきてくれる者」に分け、さらに「訪ねてくる者」を、
- ・自分も不遇なので、「いい仲間が増えた」と喜んでくる者
- ・少しは心を入れ替えておとなしくなったかな、と様子を見にくる者
- ・よからぬ企てをしているのなら、その兆候を信長に報告してやろうと偵察にくる者
- ・「だから言わないことじゃない」とシタリ顔で語る者
などに分類して、人物を見極めたという。
利家は後に、「人間は悲運の底に沈んでみなければ、友人の善悪もわからない。もっと大切なのは、その時になって初めて自分の心がわかることだ」と総括している。
また、利家には不遇経験を生かした、次のようなエピソードがある。
利家は死ぬ間際、経理担当の家臣に、今まで自分のために出させた「裏金」関係の書類を持ってこさせた。そして書類に目を通しながら、「知らなかったよ、ここまでおまえに苦労させたとは」と労をねぎらい、書類を2つに分けた。
「2つに分けた書類のうち、こっちは理由があるから支出できる。だが、こちらは無理だ。重役と相談して作り直せ」と利家は言い、さらにこう付け加えた。