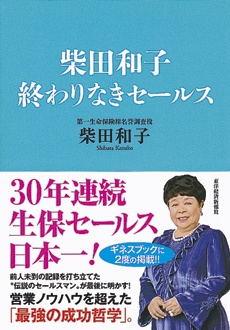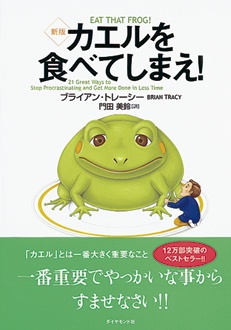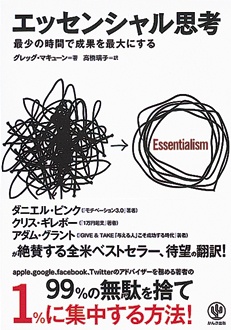2015年4月号掲載
ナンバーセンス ビッグデータの嘘を見抜く「統計リテラシー」の身につけ方
Original Title :NUMBERSENSE
- 著者
- 出版社
- 発行日2015年2月6日
- 定価1,980円
- ページ数283ページ
※『TOPPOINT』にお申し込みいただき「月刊誌会員」にご登録いただくと、ご利用いただけます。
※最新号以前に掲載の要約をご覧いただくには、別途「月刊誌プラス会員」のお申し込みが必要です。
著者紹介
概要
「ナンバーセンス」とは、統計のリテラシーのこと。問題のあるデータを見た時に何かが違うと感じる、罠を見抜く知恵だ。ビッグデータの時代、判断を誤らないためには、ナンバーセンスを磨くことが欠かせない。本書では、共同購入クーポンサイト「グルーポン」など、身近な例を基に世の中のおかしな分析を明らかにし、統計リテラシーの大切さを説く。
要約
「ナンバーセンス」とは
ビル・ゲイツの人生は、アメリカの典型的なサクセスストーリーだ。超優秀な若者が大学を退学し、起業してつくったソフトウェアは全世界のコンピュータの90%を動かすまでになった。
桁外れのカネを稼いだら早々に引退。巨額の私財を慈善活動に投じている。ビル&メリンダ・ゲイツ財団は、途上国のマラリア対策やエイズ研究などに大きな支援を行い、高く評価されている。
また、データを重視して判断を下すことでも知られている。ただし、データに基づいていれば判断を誤らない、という意味ではない。
2000年以降、ゲイツ財団は学校の小規模化を奨励し、全米で数多くの学校を支援してきた。アメリカの教育界では当時、「成績ランキングの上位に小規模な学校が多い」という統計上の発見が注目されていた。例えば、ペンシルベニア州の小学5年生のリーディングの成績は、上位50校のうち12%が小規模な学校だった。
ゲイツ財団は学校の規模がカギを握ると考え、1学年100人までを目安に、大規模な学校を分割する改革を提案した。例えば、ワシントン州のある高校の全校生徒1800人は、2003年度から5つの学校に分かれた。ゲイツ財団の教育部門の事務局長は当時、次のように説明した。
「小規模な学校は(大規模な学校に比べて)前向きな雰囲気や高い期待が生まれやすく、改良されたカリキュラムで適切な指導が行われやすい」
常に正しい答えを出せる人はいない
だが10年後、ゲイツ財団は方針を転換した。学校の規模を、成績向上の唯一の解決策と考えるのをやめたのだ。というのも、財団が調査した結果、規模を縮小した学校で生徒の成績が向上しておらず、むしろ低下した例もあったからだ。
この数百万ドル規模の判断ミスに対し、経済学者のハワード・ウェイナーは回避できたはずだと指摘した。例えば、先に挙げたペンシルベニア州の5年生のリーディングの成績は、上位50校のうち12%が小規模な学校だっただけでなく、下位50校のうち18%も小規模な学校が占めていた。つまり、最下層でも小規模な学校が多いのだ。
データのどの部分に注目するかで、分析結果が正反対になる。重要なのはどれだけ多くのデータを分析するかではなく、どのように分析するかだ。
データ分析は厄介な仕事で、常に正しい答えを出せる人などいない。官僚であれ専門家であれ、どんなに優秀な人でも間違える余地は必ずある。
学校の規模に関する分析では、小規模な学校ほど成績が良いという説は、裏づけとなる数字がなかった。学校の規模と成績の間に相関関係が存在するとしても、学校の規模が、成績という結果の原因になると結論づけるには不十分だ。