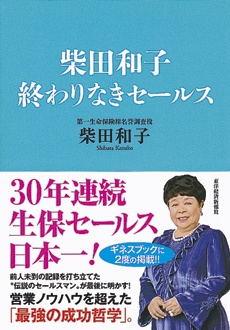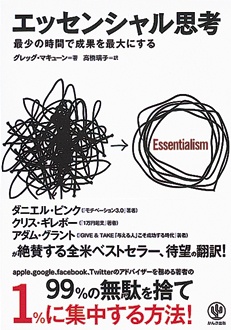2016年7月号掲載
プロの残業術
- 著者
- 出版社
- 発行日2013年6月10日
- 定価748円
- ページ数217ページ
※『TOPPOINT』にお申し込みいただき「月刊誌会員」にご登録いただくと、ご利用いただけます。
※最新号以前に掲載の要約をご覧いただくには、別途「月刊誌プラス会員」のお申し込みが必要です。
著者紹介
概要
今、残業をしない仕事術がもてはやされている。だが米国でコンサルタントとして活躍する著者によれば、残業は能力を伸ばし、頭角を現す絶好のチャンス。残業をなくすと逆にストレスがたまり、グローバルな人材競争を勝ち抜けないという。本書では、米国での経験に根差す、自分のための残業=「私的残業」の大切さを語る。
要約
「私的残業」のススメ
アメリカ発の大不況リーマン・ショック。それが上陸する前から、日本にはおかしな動きがあった。残業をするなするな、の大合唱だ。
この20年で日本は祝祭日を増やし、休日が日曜日と重なれば月曜日が休みになるという「すごい仕組み」を考えだし、さらに週休2日を当たり前にするという「職場文化革命」を断行した。
時短がそれだけ進んだのに、近年はそれが極まり、残業そのものを罪悪視する風潮である。これは、第2次職場文化革命とでもいうべきものだ。
週休2日制の導入や祝祭日の増加がいわれていた頃は、「メリハリ」が主張されていた。「やる時はやる!」という言葉が職場では聞かれた。
ところが、この第2次職場文化革命では、「効率化」が金科玉条のように主張され、残業が「おバカさんの居残り」のように位置づけられている。
ゆとりの押し売り
90年代に実施されたゆとり教育は、単に子どもの学力を下げてしまったという反省が深い。今あの頃を振り返って、「あれはあれでそれなりに意味もあった」という言説にはほとんどお目にかかれない。それもまたヘンな話だ。
時間の配分を「教育」から「別のところ」に譲ったわけだから、人間生活の別のところにメリットが生まれたはずではないのか。
これが失敗だったのは、結局、ゆとりとは役所に押しつけられて手に入るものではないからだろう。自らが欲して手に入れたものではないので、そこに価値を見いだすことができないのだ。
ゆとりに価値がないとは言わない。しかし他人が規定するゆとりの尺度など真に受けない方がいい。個人がゆとりを感じるためには、第三者的な価値観など何の役にも立たない。
実は「ゆとり教育」の失敗は、舞台を変えて我々の社会に忍び込みつつある。それは、幻想としての「ゆとり企業社会」だ。「ノー残業」を高らかに謳う社会だ。
「個人」がそれぞれのライフスタイルとして選び取るなら、ノー残業にも意味がある。だが今、メディアでは「残業をやめる」ことがことさらに美しく謳われている。残業をやめれば会社の効率が上がり、人々はゆとり企業社会の中で楽しく過ごすことができ、精神的な豊かさを得て幸福になれると、まことしやかに喧伝されている。