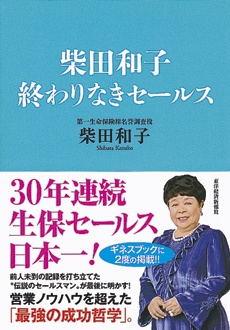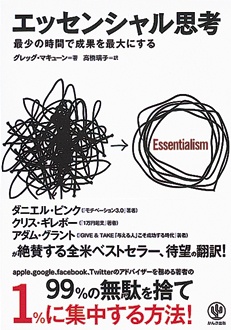2019年2月号掲載
サバイバル決断力 「優柔不断」を乗り越える最強レッスン
著者紹介
概要
決断できる人と、できない人の差。それは「リスクへの姿勢」にある。後者は、問題を検討し、取れるリスクだと判断したにもかかわらず、決めきれない。本書は、こうした優柔不断を乗り越え、優れた意思決定をするための方法を紹介。披露される枠組みと手順は、どんな状況下の意思決定にも応用でき、決断力の強化に役立つ。
要約
なぜ意思決定のトレーニングが必要か
世の中にはスパッと意思決定できる人もいれば、なかなかできない人もいる。その違いは何か?
カギを握るのは、「リスクへの姿勢」である。
意思決定できる人とは、「計算してリスクを取れる人」である。意思決定できない人はその逆で、「リスクを取れない人」だ。すなわち、分析・検討し、取れるリスクであるにもかかわらず、決定に踏み切れない人を指す。
優柔不断の原因は、性格ではなく問題にある
意思決定できない、すなわち優柔不断には2種類のタイプがある。
1つは、普段と異なる状況に遭遇した途端、何をしていいのかわからなくなってしまう「状況困惑型」タイプ。どんな状況下でも使える決定の枠組みを知らないので、意思決定できない。
もう1つは「熟慮逡巡型」タイプ。意思決定をするための材料(情報)をそろえ、どれが一番良い選択なのかほぼわかっているにもかかわらず、決定に踏み切れない。つまり、その1つを選ぶことで他の選択肢を切り捨てることができないのだ。
では、優柔不断になる原因は何か。
優柔不断は性格のせいではない。性格の問題なら、優柔不断な人は何も決められないことになる。ところが、実際にはどんな人でも、即決する場合もあれば、なかなか決められない場合もある。
優柔不断になる原因の多くは、問題そのものにある。例えば、選択肢の数が多すぎる、情報がほとんどない、といったことだ。従って、何が意思決定を困難にしているのかを分析し、意思決定の方法(後述)を身につけるよう努力することが重要だ。そうすれば、優柔不断になりそうな状況にも対処でき、中長期的に決断力が向上する。
意思決定に影響を及ぼす「確証バイアス」
人間には、仮説を検証する際、肯定的な情報ばかり集め、否定的な情報は無視する傾向がある。
例えば、ある会社で、上司から「ミャンマーに進出すべきかどうか検討してくれ」と指示されたら、担当者は勝手に「うちのトップはミャンマーに進出する気だな」と思ったりする。