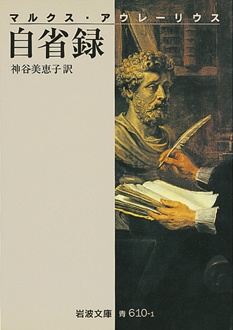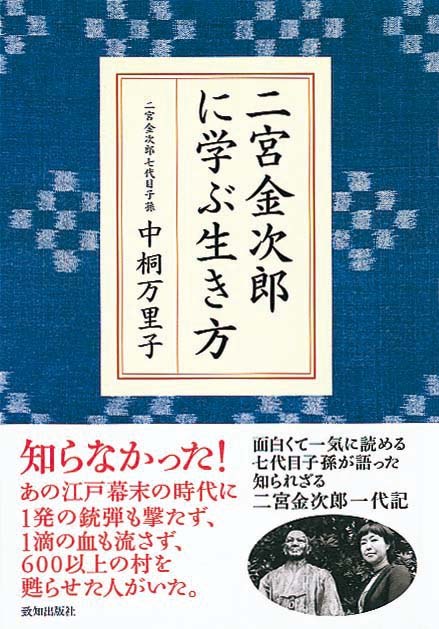2022年1月号掲載
私の親鸞 孤独に寄りそうひと
著者紹介
概要
「人は1人でいても孤独ではない。もう1人、親鸞という人物が常にそばにいてくれるからだ」。五木寛之氏、89歳。30代で出会った浄土真宗の開祖と、半世紀以上、共に歩んできた。封印し続けた過酷な引き揚げ体験、そこで抱いた罪の意識、そして心癒やされた親鸞の言葉…。“わが心の親鸞”を語った、半自伝的親鸞論である。
要約
親鸞のほうへ
70余年前の中学1年の夏、敗戦という出来事があった。それをきっかけにして旧植民地の支配者、その一族として外地に住んでいた日本人は、一夜にして難民のような状態に陥った。
私が住んでいたのは北朝鮮の平壌だが、敗戦後、引き揚げは、いっこうに始まらなかった。
私の家族も、しばらくは平壌の収容所のようなところで暮らしていたが、このまま待っていても引き揚げは期待できないということで脱北を試みた。3度目にようやく成功して、徒歩で38度線を越え、米軍の難民キャンプに収容された。
語りたくない記憶
敗戦の翌月、混乱の中で母親が亡くなり、その後は長男として、幼い妹と弟を養いながら引き揚げの日々を過ごしたが、その間にあったことは小説にも書いていない。
なぜ語りたくないか。それは、自分たちが一方的に被害を受けたわけではないからかもしれない。
私たちがかつて植民者として、かの地に君臨していた時代があった。そのこと自体が大変な負い目であり、それと同時に、戦争直後の状況下で起きた言葉にできないような様々な出来事に関して、自分が一方的被害者ではなかった。そのことを思い返すと、どうしても言葉が出てこないのだ。
例えば、国境線を越えるトラックに、「あと2人乗れるよ」と言われて、何人かが先を争って荷台によじ登ろうとする。すると先に上った2人は、後から乗ろうとする仲間を足で蹴落とす。
そんな体験をしているので、私は「日本人同士」という言葉に対して深い疑念を抱いている。そして私たちは、何かの折に、日本人でも、人間でもない存在になり果ててしまうことがある。私たちは、そういう可能性を持った生きものなのだ。
「許されざる者」としての自分
収容所では赤ん坊は栄養失調になり、ちょっと風邪を引いたぐらいでも肺炎になって死んでしまう。そういう絶望的な状況だった。
「何とかして子どもには生きていてほしい。この子を現地の人に預けたいが、誰か欲しい人を見つけてくれませんか」。子どもを抱えた母親から、そういう相談を受けることもあった。
一方、食べていくため闇市で物を売り買いしていると、現地の人から「日本人の子どもを売りたい人はいないか」と相談を受けることがあった。子どもをゆずりたい、という母親がいると、お金や食糧などと引き換えに子どもが受け渡された。