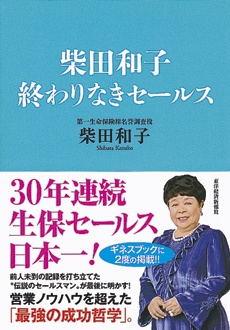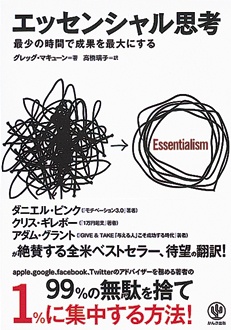2018年9月号掲載
できる人は統計思考で判断する
著者紹介
概要
「統計思考」とは、すなわち情報を客観的に分析し、適切な判断を行うための合理的な考え方だ。「どの列に並べば、一番早く自分の順番が来るか」「どれを最優先すれば、仕事が効率的に回るか」等々、暮らしやビジネスの中で何かを見極めるのに役立つ。この「強く、賢く生きる」ために有効なスキルの身につけ方を、事例を交え紹介。
要約
推測する力
今は、情報の読み取り方によって人生に大きな差がつく「情報格差社会」である。情報をどう判断するかによって、頭の使い方、時間の使い方、お金の使い方、すべてが変わる。
そんな情報格差社会を「強く、賢く生きる」上で有効なのが「統計思考」だ。これは、情報が正しいかどうかを客観的に分析し、適切な判断を行うための合理的な考え方である。例えば ――
統計データを正しく理解する
私たちは日々、数多くの「不確実な物事」に囲まれて暮らしている。「災害の予知」はおろか、「明日の天気予報」でさえ、確実とはいえない。
実は「絶対に確実な推測ができる」という方法はない。だが、推測の確実性を高める方法はある。
「推測する力」を高めるために最も重要なのは、「統計データを正しく理解すること」だ。そのためには、統計データは見せ方によって、都合よく操作できる、ということを知っておく必要がある。
例えば日本人の睡眠時間でいえば、睡眠時間の短い首都圏在住者のデータだけを標本にとると、日本人全体よりも睡眠時間を短く見せられる。一方、睡眠時間の長かった30年前のデータを使えば、現状より睡眠時間を長く見せられる。
また、平均睡眠時間は7~8時間なので、その推移をグラフで表す時、縦軸を0~10時間とすれば変化を小さく、7~9時間とすれば変化を大きく見せられる。このように恣意的に操作できるため、統計データを見る時は、標本のとり方、データの年月日、グラフの軸に注意が必要である。
その行列に「何分待つか」一瞬でわかる
物事を「ざっくりと見積もる」ことは、物事を推測する上で役に立つ。その代表例が、行列の待ち時間を推定する方法、「リトルの法則」だ。
この法則では、自分が行列に並んでから、1分間で何人が自分の後ろに並んだかを数える。そして、自分の前に並んでいる人数を数え、その人数を、1分間に自分の後ろに並んだ人数で割り算する。その答えが、待ち時間の推定結果となる。
例えば、遊園地の観覧車乗り場に約100人並んでいたとする。そして自分が列に並んだ後、1分間で5人並んだ。この時の待ち時間は、100人を5人で割ればいいので、「20分」と推定される。
「初期条件」の重要性
未来を予測するには、どうしたらよいのか?